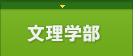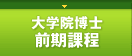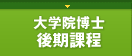検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

古典文学専門演習2
| 令和3年度以降入学者 | 古典文学専門演習2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 久保木秀夫 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 開講区分 | 文理学部 | |
| 科目群 | 国文学専攻 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業形態 | 対面授業(一部遠隔授業) |
|---|---|
| 授業の形態 | ・履修者は初回授業開始時までに必ず、Canvas LMSへの登録を済ませておくこと。 |
| 授業概要 | ・履修者各自が専門とするテーマに関する諸資料類を対象とし、書誌学・文献学に基づく実証的な調査・研究を行い、かつ得られた成果を発表し議論し、論文化していく知識と技術を身につける。 |
| 授業のねらい・到達目標 | ・専門分野、及び周辺分野の原本資料類を徹底的に調査研究していくことにより、古典文学研究に有益な情報を存分に引き出していく専門的なスキルを身に付けることができる。かつそうして得られた調査研究結果を的確に言語化・論文化することができる。 |
| 授業の形式 | 講義、演習、実習、研究 |
| 授業の方法 | ・履修者各自が調査研究対象とする作品を選定し、時に教員からも対象とすべきものを提示しつつ、写本・版本・古筆切などの実物、また時に複製・影印資料・デジタル画像といった2次的資料の書誌学・文献学的調査を行い、翻刻し、関連諸本と校合するという基礎作業を行っていく。その上で、履修者各自の研究テーマに即して、作品の解釈や表現分析、他作品との影響関係・窃取関係に関する調査研究を具体的に進めていき、発表・議論を行っていく。基本的にこの一連の流れをなるべく多く繰り返していく。 ・対面参加が困難な学生については、Canvas LMSのメール機能を用いて、事前に教員に申し出ること。個別事情を勘案し、妥当と判断されれば、zoomによるオンライン受講を認める。 |
| 履修条件 | 文学研究科・国文学専攻の博士前期課程に所属し、古典文学を専門分野とし、かつ科目担当者である久保木が主査の学生のみ履修可。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
ガイダンス:授業形式・内容の確認、履修者各自の専門分野・研究対象、また研究計画・到達目標の検討など。
【事前学習】履修者各自の研究テーマを具体的に検討しておく。 (2時間) 【事後学習】ガイダンスの内容を踏まえ、種々の不足分を補っておく。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 2 |
研究テーマの検討①中古・中世文学を中心に
【事前学習】先行研究を収集し、読み込んでおく。 (2時間) 【事後学習】さらなる先行研究の収集・精読を行う。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 3 |
研究テーマの検討②和歌文学を中心に
【事前学習】先行研究を収集し、読み込んでおく。 (2時間) 【事後学習】さらなる先行研究の収集・精読を行う。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 4 |
研究対象とする原本資料の選定①中古・中世文学を中心に
【事前学習】関連する原本資料の所在情報を調べておく。 (2時間) 【事後学習】閲覧・調査の可否、及び可の場合の申請方法を調べる。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 5 |
研究対象とする原本資料の選定②和歌文学を中心に
【事前学習】関連する原本資料の所在情報を調べておく。 (2時間) 【事後学習】閲覧・調査の可否、及び可の場合の申請方法を調べる。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 6 |
原本資料類の調査①中古・中世文学を中心に
【事前学習】調査対象に関する諸情報を事前に点検しておく。 (2時間) 【事後学習】調査結果から得られた諸情報を検討・分析する。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 7 |
原本資料類の調査②和歌文学を中心に
【事前学習】前回の成果をまとめておく。 (2時間) 【事後学習】調査結果から得られた諸情報を検討・分析する。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 8 |
調査・研究成果の発表と議論①
【事前学習】前回までの成果に基づき発表資料を作成する。 (2時間) 【事後学習】議論を踏まえて発表内容をブラッシュアップする。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 9 |
原本資料類の翻刻
【事前学習】調査対象に関する諸情報を事前に点検しておく。 (2時間) 【事後学習】調査結果から得られた諸情報を検討・分析する。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 10 |
校訂・解釈
【事前学習】前回の成果をまとめておく。 (2時間) 【事後学習】調査結果から得られた諸情報を検討・分析する。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 11 |
校訂本文と他作品との比較検討
【事前学習】前回までの成果に基づき発表資料を作成する。 (2時間) 【事後学習】議論を踏まえて発表内容をブラッシュアップする。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 12 |
校訂本文の表現分析
【事前学習】調査対象に関する諸情報を事前に点検しておく。 (2時間) 【事後学習】調査結果から得られた諸情報を検討・分析する。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 13 |
比較分析結果に関する議論
【事前学習】前回の成果をまとめておく。 (2時間) 【事後学習】調査結果から得られた諸情報を検討・分析する。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 14 |
議論を踏まえての追加調査・考察
【事前学習】前回までの成果に基づき発表資料を作成する。 (2時間) 【事後学習】議論を踏まえて発表内容をブラッシュアップする。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| 15 |
総括:本授業における成果の確認と今後の研究計画の策定
【事前学習】これまでの調査・研究・発表成果を再確認しておく。 (2時間) 【事後学習】総括を踏まえて成果を原稿化する。 (2時間) 【授業形態】対面授業 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 笠間影印叢刊刊行会 『字典かな―出典明記』 笠間書院 1972年 配付資料は各回の授業前にOneDriveの共有フォルダにアップし、LINE で連絡するので、各自ダウンロード(また環境的に可能であればプリントアウト)して持参すること。 |
| 参考書 | 堀川貴司 『書誌学入門 古典籍を見る・知る・読む』 勉誠出版 2010年 その他、授業中に適宜紹介していく。 |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート:授業内で積み上げてきた各自の調査研究成果について実証的に論述する。(40%)、授業参画度:調査・研究・発表・議論などへの参画度・積極性から総合的に判断する。(60%) |
| オフィスアワー | 随時授業の前後や LINE で受け付ける。 |