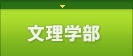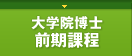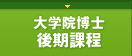検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

地球科学演習1
| 令和元年度以前入学者 | 地球科学演習1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 竹内真司 | ||||
| 単位数 | 1 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地球科学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業の形態 | オンデマンドとZoomを組み合わせて行う。またデータ取得のための対面授業をを行うことがある。さらに課題研究にてレポート作成を行う。 Blackboard ID:20212803 |
|---|---|
| 授業概要 | 地圏環境に関するデータを取得し、得られたデータに基づいて分析や解析を行う。さらに、分析・解析結果について考察する。 |
| 授業のねらい・到達目標 | ねらい: 地圏環境(地表および地下環境)に関するデータの計測方法および処理方法をそれらの基本的な考え方と合わせて習得する。得られた結果について自ら考える力を身につける。 到達目標: 1.離散データの空間補間方法について理解し、説明、解釈ができる。(1-5) 2.地質調査結果に基づいて、地質図、地質柱状図、地質断面図を作成し、調査地点の地質形成史を推定することができる。(6-10) 3.岩石を観察し、その特徴を記載し、由来や履歴を推定することができる。(11-15) ※括弧内の数字は講義番号 学科プログラム(JABEE認定プログラム含む)の学習・教育到達目標:「(G)専門知識」に寄与する。 地球科学科 ディプロマ・ポリシー(D.P.):「(G)地球科学の専門知識を修得している」に対応する。なお、学科D.P.については、平成31年度入学生学部要覧の地球科学科の「学習・教育到達目標を達成するために必要な授業科目の流れ」(https://earth.chs.nihon-u.ac.jp/curriculum/jabeeのページの「T01_学部要覧」から)を参照してください。 この科目は文理学部(学士(理学))のディプロマポリシーDP6, 及びカリキュラムポリシーCP9に対応しています。 |
| 授業の方法 | 授業の形式:【講義,実習など】 ・本授業の事前・事後学習は,各1時間の学習を目安とします。 ・データ取得のための対面授業の欠席者には、実習内容を撮影した画像や動画を別途配信する。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
全体概要、データの空間補間の方法(同時双方向型)
【事前学習】シラバスに目を通しておくこと。データの空間補間の方法について調べておくこと。 (1時間) 【事後学習】データの空間補間方法についてまとめておくこと。 (1時間) |
| 2 |
文理学部構内の空間放射線量率の測定(1)(実習)
【事前学習】福島第一原子力発電所事故による放射性物質の放出の経緯について調べておくこと。 (1時間) 【事後学習】空間放射線量率の測定方法と測定結果をまとめておくこと。 (1時間) |
| 3 |
文理学部構内の空間放射線量率の測定(2)(実習)
【事前学習】福島第一原子力発電所事故によって放出された放射性物質の移行経緯について調べておくこと。 (1時間) 【事後学習】空間放射線量率の測定結果についてまとめておくこと。 (1時間) |
| 4 |
取得データ(離散データ)の補完処理(同時双方向型)
【事前学習】取得したデータを未取得領域に補間する方法について調べておくこと。 (1時間) 【事後学習】データの補完方法のまとめるとともに、補完結果を分かりやすく表示しておくこと。 (1時間) |
| 5 |
結果の解釈、レポートの作成(課題研究)
【事前学習】空間放射線量率の空間補間結果の特徴についてまとめて考察しておくこと。 (1時間) 【事後学習】空間線量率の分布の特徴に基づいて、事故の文理学部への影響を考察すること。 (1時間) |
| 6 |
地質記載1(実習)
【事前学習】実習地点の地質について調べておくこと。 (1時間) 【事後学習】記載結果についてまとめておくこと。 (1時間) |
| 7 |
地質記載2(実習)
【事前学習】地質図の作成方法について調べておくこと。 (1時間) 【事後学習】記載結果についてまとめておくこと。 (1時間) |
| 8 |
地質記載3(実習)
【事前学習】地質断面図、地質柱状図の作成方法について調べておくこと。 (1時間) 【事後学習】記載結果についてまとめておくこと。 (1時間) |
| 9 |
地質図、地質断面図、地質柱状図の作成(実習)
【事前学習】地質図の作成方法について調べておくこと。 (1時間) 【事後学習】地質図、地質断面図、地質柱状図の作成方法についてまとめておくこと。 (1時間) |
| 10 |
地質調査結果の解釈まとめ(課題学習)
【事前学習】地質調査結果について整理しておくこと。 (1時間) 【事後学習】地質調査結果の適切性を既存の地質図等と比較・確認し、重要と思われる点についてまとめておくこと。 (1時間) |
| 11 |
岩石の観察・記載(1)(実習)
【事前学習】岩石の種類と形成過程について調べておくこと。 (1時間) 【事後学習】観察・記載した結果を分かりやすく整理しておくこと。 (1時間) |
| 12 |
岩石の観察・記載(2)(実習)
【事前学習】岩石の観察・記載方法について調べておくこと。 (1時間) 【事後学習】観察・記載した結果を分かりやすく整理しておくこと。 (1時間) |
| 13 |
記載した岩石の薄片作成(実習)
【事前学習】岩石薄片の作成方法について調べておくこと。 (1時間) 【事後学習】岩石薄片を完成させておくこと。 (1時間) |
| 14 |
記載した岩石の薄片観察(実習)
【事前学習】岩石薄片の観察方法について調べておくこと。 (1時間) 【事後学習】岩石薄片の観察結果についてまとめておくこと。 (1時間) |
| 15 |
岩石の観察・記載、薄片作成・観察結果について解釈し、レポートとしてまとめること(課題学習)
【事前学習】岩石、薄片の観察結果についてまとめておくこと。 (1時間) 【事後学習】まとめた結果と既存研究事例と比較して、重要な点についてまとめておくこと。 (1時間) |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用しない |
| 参考書 | 使用しない |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(100%) レポート(100%) 総合的に判断し60点以上を合格とする。 達成度評価基準: 1.離散データの空間補間方法について正しく理解できている。(1-5) 2.地質調査結果に基づいて、地質図、地質柱状図、地質断面図を作成し、調査地点の地質形成史を推定することができている。(6-10) 3.岩石を観察し、その特徴を記載し、由来や履歴を推定することができている。(11-15) ※括弧内の数字は講義番号 対面参加できない場合については、初回で説明する。 |
| オフィスアワー | 原則として、当該授業日に対応する。また、随時、メールにて質問を受け付ける。 |