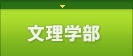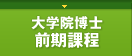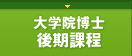検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

地理学課題研究1
| 令和元年度以前入学者 | 地理学課題研究1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 落合康浩 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地理学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業の形態 | 原則、オンラインによる同時双方向型(zoomを使ったゼミナール形式)で実施する。また、対面型で個別指導を行う(事前に入構申請・連絡をする)ことがある。なお、感染症等の状況を判断し、通常通り対面型で行うゼミナール形式の授業に戻すことがありうる。 Blackboard ID:20212668 |
|---|---|
| 授業概要 | 研究方法を学び研究課題について考えるゼミナール形式の授業 |
| 授業のねらい・到達目標 | 研究テーマに関する文献の検索・読解、資料の収集と分析方法、現地調査の方法などを学ぶとともに、それらに関する発表・討論をすることで、各自の「卒業研究」に結びつく研究課題について検討できるようになる。 この科目は文理学部(学士(地理学))のディプロマポリシーDP3,DP4,DP5,DP7及びカリキュラムポリシーCP3,CP4,CP7に対応している。(入手した客観的な情報を基に、論理的、批判的な思考をすることができる(A-3-3)。資料や事象を注意深く観察・検討して、問題を発見し、解決策を考案することができる(A-4-3)。地理学分野の課題の中から、自らが取り組むべき課題を見出し、その方法について考えることができる(A-5-3)。集団活動の中で連携しつつ、それぞれの役割について考え、効果的な協働の方法を実践することができる(A-7-3)。) |
| 授業の方法 | 提示された課題に対する各自の発表や共通課題に関する討論等により、ゼミナール形式の授業を行う。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
ガイダンス:研究課題設定に向けての手順
【事前学習】自身の研究テーマについて検討しておく。 (2時間) 【事後学習】研究テーマ設定に向けての計画を立てる。 (2時間) |
| 2 |
研究テーマに関する文献検索とそのまとめ方を学ぶ
【事前学習】文献の検索方法を理解しておく。 (1時間) 【事後学習】自身の研究テーマに関する文献を検索、入手する。 (3時間) |
| 3 |
文献の検索と読解① 第1グループの報告と質疑応答
【事前学習】自身の研究テーマに関する文献を読み、内容をまとめる。 (2時間) 【事後学習】文献をさらに読みすすめ、自身の研究テーマ設定の参考にする。 (2時間) |
| 4 |
文献の検索と読解② 第2グループの報告と質疑応答
【事前学習】自身の研究テーマに関する文献を読み、内容をまとめる。 (2時間) 【事後学習】文献をさらに読みすすめ、自身の研究テーマ設定の参考にする。 (2時間) |
| 5 |
文献の検索と読解③ 第3グループの報告と質疑応答
【事前学習】自身の研究テーマに関する文献を読み、内容をまとめる。 (2時間) 【事後学習】文献をさらに読みすすめ、自身の研究テーマ設定の参考にする。 (2時間) |
| 6 |
研究テーマに関する資料収集および分析の仕方を学ぶ
【事前学習】自身の研究テーマを絞り込む。 (1時間) 【事後学習】自身の研究テーマに必要な資料とその分析方法を考える。 (3時間) |
| 7 |
資料の収集と分析方法① 第1グループの報告と質疑応答
【事前学習】基本的な資料を収集し、その分析を行う。 (2時間) 【事後学習】発表で指摘された点にも考慮しながら、さらに分析を進める。 (2時間) |
| 8 |
資料の収集と分析方法② 第2グループの報告と質疑応答
【事前学習】基本的な資料を収集し、その分析を行う。 (2時間) 【事後学習】発表で指摘された点にも考慮しながら、さらに分析を進める。 (2時間) |
| 9 |
資料の収集と分析方法③ 第3グループの報告と質疑応答
【事前学習】基本的な資料を収集し、その分析を行う。 (2時間) 【事後学習】発表で指摘された点にも考慮しながら、さらに分析を進める。 (2時間) |
| 10 |
調査対象地域の選定の仕方と調査方法を学ぶ
【事前学習】研究テーマと資料分析の結果を整理する。 (1時間) 【事後学習】研究テーマに相応しい研究方法を考える。 (3時間) |
| 11 |
調査地域と調査方法① 第1グループの報告と質疑応答
【事前学習】調査地域と調査方法について検討する。 (2時間) 【事後学習】発表で指摘された点にも考慮しながら、調査地域・方法をさらに検討する。 (2時間) |
| 12 |
調査地域と調査方法② 第2グループの報告と質疑応答
【事前学習】調査地域と調査方法について検討する。 (2時間) 【事後学習】発表で指摘された点にも考慮しながら、調査地域・方法をさらに検討する。 (2時間) |
| 13 |
調査地域と調査方法③ 第3グループの報告と質疑応答
【事前学習】調査地域と調査方法について検討する。 (2時間) 【事後学習】発表で指摘された点にも考慮しながら、調査地域・方法をさらに検討する。 (2時間) |
| 14 |
調査地域と調査方法について討論・検討する
【事前学習】調査地域と調査方法について検討する。 (2時間) 【事後学習】討論の中で指摘された点にも考慮しながら、調査地域・方法をさらに検討する。 (2時間) |
| 15 |
まとめ:研究課題と調査方法の整理(A-3,A-4,A-5,A-7)
【事前学習】調査地域における具体的な調査内容を挙げてみる。 (2時間) 【事後学習】調査地域・調査方法に相応しい具体的な調査内容を整理する。 (2時間) |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用しない |
| 参考書 | 授業中に適宜紹介する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(30%)、授業参画度:課題に対する取り組みや報告の内容(40%)、調査・研究の進捗状況(30%) レポートは期末における最終レポート |
| オフィスアワー | 水曜日・金曜日12:10~13:00 8号館4階A408研究室 |
| 備考 | 夏期休業中に共通課題による巡検を予定している(対面式授業および出張が可能になった場合)。また、4年生との合同ゼミも開催する予定。 |