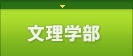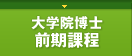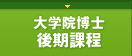検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

日本史研究法入門
| 令和2年度以降入学者 | 日本史研究法入門 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年度以前入学者 | 日本史入門 | ||||
| 教員名 | 武井紀子 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 史学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業の形態 | 課題研究:Blackboardを通じたオンデマンド型授業 Blackboard ID:20211242 |
|---|---|
| 授業概要 | 日本史研究の基礎を学ぶ |
| 授業のねらい・到達目標 | 日本史を研究する上での留意すべき点や、さまざまな研究視角、研究方法を学ぶ。日本史研究上の争点、各時代の史料状況、辞典類、文書館・史料館、公的機関のインターネットサイトにどのようなものがあり、どう使えるかという、研究の基礎知識を習得する。 ・現代社会における人文学・歴史学の役割を理解し、そのことを踏まえて、日本史研究の観点から国際社会が直面している問題を説明することができる(A-2-2)。 ・既存の知識にとらわれることなく、日本史研究の方法を踏まえて、物事を論理的・批判的に説明することができる(A-3-2)。 この科目は、文理学部史学科(学士(文学))のディプロマポリシーDP2、3、及びカリキュラムポリシーCP2、3に対応しています。 |
| 授業の方法 | 授業の形式:【講義】 Blackboardを通じたオンデマンド型課題研究。 毎回音声と資料を配布し、授業内容に対するコメントや質問を課題として提出してもらい(リアクションペーパー、毎回200字程度)、それらに対するフィードバックを次の授業音声あるいはBbの掲示板を用いて行う。これまでの日本史研究の成果を、論争点などを中心に振り返り、また研究の基礎となる史料や専門的な事典類を紹介しながら、日本史研究の現状と到達点を考える。授業内に紹介する文献を自分で実際に読み、問題点を見いだしていく努力が必要である。本授業の1回ごとの事前・事後学習は、合計4時間の学習を目安とする。資料と音声は本来の時限(月曜2限)の開始時間(午前10時40分)までに配信し、リアクションペーパー提出締切は水曜日夜の予定。授業内テストと解説は、当該週の本来の時間帯(月曜2限)に行う。 *履修者は初回講義開始までにBlackboardのコース登録をすること。また受講者への連絡もBlackboardの「連絡事項」欄に掲示する場合があるので、随時確認すること。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
日本史の地理的範囲(A2-2)
【事前学習】日本の範囲の歴史的変遷を調べる。 (0.5時間) 【事後学習】授業内容を整理しておく。 (1時間) |
| 2 |
日本史研究の基礎知識(A2-2)
【事前学習】暦の変化と十干十二支について調べる。 (1時間) 【事後学習】授業内容を整理しておく。 (1時間) |
| 3 |
日本史の時代区分(A2-2)
【事前学習】古代・中世・近世・近代という言葉の意味について調べる。 (1時間) 【事後学習】授業内容を整理しておく。 (1時間) |
| 4 |
古代史研究の争点(A2-3)
【事前学習】大化改新論争について調べる。 (1時間) 【事後学習】授業で紹介された文献を読んでみる。 (3時間) |
| 5 |
中世史研究の争点(A2-3)
【事前学習】権門体制論について調べる。 (1時間) 【事後学習】授業で紹介された文献を読んでみる。 (3時間) |
| 6 |
近世史研究の争点(A2-3)
【事前学習】鎖国と四つの口について調べる。 (1時間) 【事後学習】授業で紹介された文献を読んでみる。 (3時間) |
| 7 |
近現代史研究の争点(A2-3)
【事前学習】歴史認識論争について調べる。 (1時間) 【事後学習】授業で紹介された文献を読んでみる。 (3時間) |
| 8 |
歴史書の編纂(A2-2)
【事前学習】六国史について調べる。 (1時間) 【事後学習】授業で紹介された史料を図書館等で読んでみる。 (3時間) |
| 9 |
一次史料と二次史料(A2-2)
【事前学習】一次史料と二次史料にはどのようなものがあるかについて調べる。 (1時間) 【事後学習】授業で紹介された史料を図書館等で読んでみる。 (3時間) |
| 10 |
史料として日記を読む(A2-2)
【事前学習】古代から近現代までの日記にどのようなものがあるかについて調べる。 (1時間) 【事後学習】授業で紹介された史料を図書館等で読んでみる。 (3時間) |
| 11 |
文献史料・出土文字資料の調査方法(A2-2)
【事前学習】文献史料・出土文字資料の資料としての特徴について調べる。 (1時間) 【事後学習】授業で紹介された史料を図書館等で読んでみる。 (3時間) |
| 12 |
道具類(事典)と史料館・文書館(A2-2)
【事前学習】東京大学史料編纂所・アジア歴史資料センターのホームページを探索しておく。 (1時間) 【事後学習】授業で紹介された事典類やホームページを見てみる。 (3時間) |
| 13 |
時代をまたぐ争点「天皇」(A2-2)
【事前学習】歴史事典で「天皇」について調べる。 (1時間) 【事後学習】授業で紹介された文献を読んでみる。 (3時間) |
| 14 |
授業内テストと問題の解説(A2-2、3)
【事前学習】前回までの授業内容を整理復習する。 (7時間) 【事後学習】解説を復習しておく。 (0.5時間) |
| 15 |
テスト答案に対する総評と授業全体のまとめ(A2-3)
【事前学習】日本史研究法の特徴について考えをまとめておく。 (0.5時間) 【事後学習】今後の学修に役立つよう、授業内容全体を整理しておく。 (2.5時間) |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 教科書は使用しない。 |
| 参考書 | 中公新書編集部 『日本史研究の論点 (中公新書)』 中公新書 2018年 五味文彦・杉森哲也 『日本史史料論 (放送大学大学院教材)』 NHK出版 2015年 大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市 『岩波講座 日本歴史 全22巻』 岩波書店 2013年 その他、授業中に適宜紹介する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト:授業内テストは論述複数題、毎回の事後学習に関する出題もありえる。持ち込み自由。(60%)、授業参画度:授業参画度は、毎回のリアクションペーパーにより評価する。(40%) |
| オフィスアワー | blackboardの掲示板、あるいは教員へのメールにて受け付ける。 |