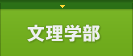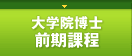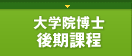検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

比較教育学特論2
| 科目名 | 比較教育学特論2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 間篠剛留 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業概要 | 先行研究検討の方法を学ぶ |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 本科目では、履修者の関心に沿ってリストアップされた比較教育学の研究論文を相互検討する。検討対象となる文献は、履修者が修士論文・博士論文を執筆する際に先行研究となるようなものを想定している。それらについて、その意義や価値、および課題を検討する。自らの関心に沿って文献を読むだけでなく、他者の関心に沿った文献も読み、相互討論を重ねることで、比較教育学の現在についての包括的な理解を目指したい。また、先行研究が自らを大きな研究の文脈にどのように位置づけているかについての検討を重ねることで、履修者自身の修士論文・博士論文の位置づけの検討を深めたい。 |
| 授業の方法 | 第2・3回の授業で各人の関心に基づく文献リストの紹介を行う。第4~14回では、それらの文献を全体で検討していく。担当者は担当回の1週前には文献を共有すること。 |
| 履修条件 | 特になし |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
イントロダクション(授業のテーマや到達目標及び授業の方法についての説明)及び各人の研究関心の紹介 【事前学習】自身の研究テーマについて説明準備を行う。 【事後学習】文献リストの作成 |
| 2 |
文献リストの紹介 【事前学習】発表準備 【事後学習】他の履修者の発表を参考に、自身のリストを修正する |
| 3 |
文献リストの紹介、担当の割り振り 【事前学習】発表準備 【事後学習】他の履修者の発表を参考に、自身のリストを修正する |
| 4 |
文献講読(1) 【事前学習】課題文献の通読 【事後学習】文献の読み方の確認 |
| 5 |
文献講読(2) 【事前学習】課題文献の通読 【事後学習】文献の読み方の確認 |
| 6 |
文献講読(3) 【事前学習】課題文献の通読 【事後学習】文献の読み方の確認 |
| 7 |
文献講読(4) 【事前学習】課題文献の通読 【事後学習】文献の読み方の確認 |
| 8 |
文献講読(5) 【事前学習】課題文献の通読 【事後学習】文献の読み方の確認 |
| 9 |
文献講読(6) 【事前学習】課題文献の通読 【事後学習】文献の読み方の確認 |
| 10 |
文献講読(7) 【事前学習】課題文献の通読 【事後学習】文献の読み方の確認 |
| 11 |
文献講読(8) 【事前学習】課題文献の通読 【事後学習】文献の読み方の確認 |
| 12 |
文献講読(9) 【事前学習】課題文献の通読 【事後学習】文献の読み方の確認 |
| 13 |
文献講読(10) 【事前学習】課題文献の通読 【事後学習】文献の読み方の確認 |
| 14 |
文献講読(11) 【事前学習】課題文献の通読 【事後学習】文献の読み方の確認 |
| 15 |
総括討論(自分の研究の位置づけについて) 【事前学習】自分の研究が研究史の中にどう位置づくのか考える |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用しない |
| 参考書 | 大学教育学会 『大学教育学会誌』 日本高等教育学会 『高等教育研究』 日本比較教育学会 『比較教育学研究』 |
| 成績評価の方法及び基準 | 授業参画度(50%)、文献リスト(50%) 授業参加度は、授業における課題発表、討論等によって総合的に判断する。 |
| オフィスアワー | 水曜日4時限目 |