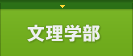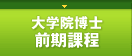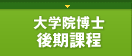検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

日本史特殊講義1
| 科目名 | 日本史特殊講義1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 上保國良 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 史学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業概要 | 川柳による江戸案内、江戸紹介を読む(その1)。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 江戸ッ子のユーモアを体得し、併せて近世文芸の史料としての性格について説明できるようになる(その1)。 |
| 授業の方法 | 江戸川柳に関する配布プリントを講読する(その1)。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 教材プリントを配布し、その利用方法について説明する。 |
| 2 | 詠史・雑俳・狂歌・落首等について解説する。 |
| 3 | 配布プリントの空白部に充当する地名等の用語に関する参考文献・資料等について案内する。 |
| 4 | 一例として、教材プリントの特定空白部に用語を充当させ、その川柳の類句・関連句等について講じてみる。 |
| 5 | 受講院生に教材プリントより興味ある川柳を選択させ、発表順を決める。なお、発表の際には「レジュメ」を用意することを申し伝え、その要領については、次回に説明する旨を伝える。 |
| 6 |
発表レジュメについて、以下の点の重要性について説明する。 ①当該川柳の出典を明らかにし、大意を述べる。 ②当該川柳の類句を出典を明らかにしつつ、出来るだけ多くあげてみる。 ③当該川柳の関連句について出典を明らかにしつつ、出来るだけ多くあげてみる。 ④当該川柳の地点に関する絵画史料を示す。 |
| 7 |
第一発表者がこれまでの注意をもとにレジュメを作成し、自分が選択した川柳について説明していく。教員ならびに他の受講院生はその説明やレジュメに意義があれば申し立てて、意見を述べたり、討論に入る。 ※通常、発表者が交代するには最低3回は要している。 |
| 8 |
第一発表者の発表のつづきを行う。前回同様に、教員ならびに他の受講院生は、その説明やレジュメに意義があれば申し立てて、意見を述べたり、討論に入る。 ※通常、発表者が交代するには最低3回は要している。 |
| 9 |
第一発表者の発表のつづきを行う。教員ならびに他の受講院生は説明やレジュメに意義があれば申し立てて意見を述べたり、討論に入る。 ※発表者はこれまでの遣り取りを踏まえて、レジュメの完成原稿を時宗までに担当教員に提出する。 |
| 10 | 第二発表者の発表に入る。内容は第一発表者の第一回目のことと同じで、その回を参照すること。 |
| 11 | 第二発表者の発表のつづきを行う。内容は第一発表者の第二回目のことと同じで、その回を参照すること。 |
| 12 |
第二発表者の発表のつづきを行う。内容は第一発表者の第三回目のことと同じで、その回を参照すること。 ※レジュメの提出についても同様である。 |
| 13 | 第三発表者の発表に入る。内容は第一発表者・第二発表者の第一回目のことと同じで、その回を参照すること。 |
| 14 | 第三発表者の発表のつづきを行う。内容は第一発表者・第二発表者ののことと同じで、その回を参照すること。 |
| 15 |
第三発表者の発表のつづきを行う。内容は第一発表者・第二発表者のことと同じで、その回を参照すること。 ※レジュメの完成原稿は、1週間以内に史学研究室に提出すること。 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | プリントを配布する。 |
| 参考書 | 使用しない |
| 成績評価の方法及び基準 | 授業レジュメの完成度(80%)、授業参画度(討論参画度)(20%) |
| オフィスアワー | 授業終了後 |
| 備考 | 受講院生の人数によっては予定が変わることがある。 |