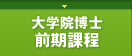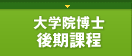検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

卒業論文
| 科目名 | 卒業論文 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 立道信吾 | ||||
| 単位数 | 8 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 社会学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業概要 | 卒業論文を完成させるまでの一連の準備、作業を学び、卒業論文を完成させる。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 卒業論文を完成させるための、テーマの選び方、文献資料の渉猟の仕方、文章の書き方、論文のスタイルガイドの基本などを学ぶと共に、毎回の授業で、履修者が自分の卒論の進捗状況についての報告を行い、参加者全員がテーマについて議論します。 この科目は文理学部(学士(社会学))のディプロマポリシーDP3及びカリキュラムポリシーCP5に対応しています。 |
| 授業の方法 | 卒論執筆の基本について座学で学ぶと共に、毎回の授業で履修者が交代で自分の研究テーマについて発表し、全員で議論するとともに、完成に向けてのアドバイスを教員が行います。このため、シラバスの毎回の授業の覧には決まったテーマ、課題を記しておりません。 本授業の事前・事後学習は,各3時間の学習を目安とします。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
卒業論文とは何か 【事前学習】 自分が書きたいと思う卒論のテーマについて、いくつかの案を考える。 【事後学習】 授業で習ったことをノートに整理する。 |
| 2 |
テーマをどのように決めるか 【事前学習】 卒業生の卒論のテーマ一覧を見る。 【事後学習】 興味のあるテーマについてインターネット等で情報を収集する。 |
| 3 |
文献サーベイの方法 【事前学習】 「アカデミック・スキルズ(第2版)――大学生のための知的技法入門」など、アカデミックスキルに関する本を読んでおく。 【事後学習】 CINIIを使って、興味のある論文の検索を行う。 |
| 4 |
論文の構成 【事前学習】 「アカデミック・スキルズ(第2版)――大学生のための知的技法入門」など、アカデミックスキルに関する本を読んでおく。 【事後学習】 自分の論文をどのような構成にするか考えてみる。 |
| 5 |
受講生によるテーマの発表・前半 【事前学習】 自分の研究テーマの発表に向けた資料を作成する。 【事後学習】 自分の研究テーマに関する教員のコメントを参考に、テーマを再考する。 |
| 6 |
受講生によるテーマの発表・後半 事前学習】 自分の研究テーマの発表に向けた資料を作成する。 【事後学習】 自分の研究テーマに関する教員のコメントを参考に、テーマを再考する。 |
| 7 |
社会学評論スタイルガイドから卒論の作法を学ぶ①一般的な表記 【事前学習】 社会学評論スタイルガイドの表記の仕方を読む。 【事後学習】 『社会学評論』のバックナンバーを見て、表記の仕方を確認する。 |
| 8 |
社会学評論スタイルガイドから卒論の作法を学ぶ②文献や注の表記 【事前学習】 社会学評論スタイルガイドの表記の仕方を読む。 【事後学習】 『社会学評論』のバックナンバーを見て、表記の仕方を確認する。 |
| 9 |
研究テーマ・問題意識についての受講生の発表①以下は、受講生が多いため3回に分けて発表を行う 【事前学習】 自分の発表する研究テーマについての資料を作成する。 【事後学習】 自分の発表に対する批判・コメント等を元に研究テーマを再考する。 |
| 10 |
研究テーマ・問題意識についての受講生の発表② 【事前学習】 自分の発表する研究テーマについての資料を作成する。 【事後学習】 自分の発表に対する批判・コメント等を元に研究テーマを再考する。 |
| 11 |
研究テーマ・問題意識についての受講生の発表③ 【事前学習】 自分の発表する研究テーマについての資料を作成する。 【事後学習】 自分の発表に対する批判・コメント等を元に研究テーマを再考する。 |
| 12 |
先行研究についての受講生の発表①以下は、受講生が多いため3回に分けて行う。 【事前学習】 自分の発表する研究テーマについての資料を作成する。 【事後学習】 自分の発表に対する批判・コメント等を元に研究テーマを再考する。 |
| 13 |
先行研究についての受講生の発表② 【事前学習】 自分の発表する研究テーマについての資料を作成する。 【事後学習】 自分の発表に対する批判・コメント等を元に研究テーマを再考する。 |
| 14 |
先行研究についての受講生の発表③ 【事前学習】 自分の発表する研究テーマについての資料を作成する。 【事後学習】 自分の発表に対する批判・コメント等を元に研究テーマを再考する。 |
| 15 |
執筆計画についての指導 【事前学習】 卒論の章立ての案を考えておく。 【事後学習】 教員の指導に基づき、章立てを再考する。夏休み中の作業計画を立て、計画にそって卒論を進める。 |
| 16 |
本論部分についての受講生の発表① ①以下は、受講生が多いため6回に分けて発表を行う 【事前学習】 自分の発表する研究テーマについての資料を作成する。 【事後学習】 自分の発表に対する批判・コメント等を元に卒論の本論部分を再考する。 |
| 17 |
本論部分についての受講生の発表② 【事前学習】 自分の発表する研究テーマについての資料を作成する。 【事後学習】 自分の発表に対する批判・コメント等を元に卒論の本論部分を再考する。 |
| 18 |
本論部分についての受講生の発表③ 【事前学習】 自分の発表する研究テーマについての資料を作成する。 【事後学習】 自分の発表に対する批判・コメント等を元に卒論の本論部分を再考する。 |
| 19 |
本論部分についての受講生の発表④ 【事前学習】 自分の発表する研究テーマについての資料を作成する。 【事後学習】 自分の発表に対する批判・コメント等を元に卒論の本論部分を再考する。 |
| 20 |
本論部分についての受講生の発表⑤ 【事前学習】 自分の発表する研究テーマについての資料を作成する。 【事後学習】 自分の発表に対する批判・コメント等を元に卒論の本論部分を再考する。 |
| 21 |
本論部分についての受講生の発表⑥ 【事前学習】 自分の発表する研究テーマについての資料を作成する。 【事後学習】 自分の発表に対する批判・コメント等を元に卒論の本論部分を再考する。 |
| 22 |
執筆内容についての指導① 以下は、受講生が多いため4回に分けて行う。 【事前学習】 執筆上の問題点、疑問点についての教員への質問を整理しておく。 【事後学習】 教員の指示に従って、必要な修正等を行う。 |
| 23 |
執筆内容についての指導② 【事前学習】 執筆上の問題点、疑問点についての教員への質問を整理しておく。 【事後学習】 教員の指示に従って、必要な修正等を行う。 |
| 24 |
執筆内容についての指導③ 【事前学習】 執筆上の問題点、疑問点についての教員への質問を整理しておく。 【事後学習】 教員の指示に従って、必要な修正等を行う。 |
| 25 |
執筆内容についての指導④ 【事前学習】 執筆上の問題点、疑問点についての教員への質問を整理しておく。 【事後学習】 教員の指示に従って、必要な修正等を行う。 |
| 26 |
中間報告会①以下は受講生が多いため3回に分けて行う 【事前学習】 卒論のドラフト原稿に基づき、発表内容を整理しておく。 【事後学習】 教員や受講生からの批判・コメントに基づき論文に必要な修正を行う。 |
| 27 |
中間報告会② 【事前学習】 卒論のドラフト原稿に基づき、発表内容を整理しておく。 【事後学習】 教員や受講生からの批判・コメントに基づき論文に必要な修正を行う。 |
| 28 |
中間報告会③ 【事前学習】 卒論のドラフト原稿に基づき、発表内容を整理しておく。 【事後学習】 教員や受講生からの批判・コメントに基づき論文に必要な修正を行う。 |
| 29 |
推敲の方法 卒業論文原稿の最終チェック 【事前学習】 推敲の方法についてインターネットで検索しておく。 【事後学習】 授業中の教員の指示に基づき推敲を行う。 |
| 30 |
卒業論文の提出と日本語ならびに英語による要約の作成 【事前学習】 論文の要約の作成 【事後学習】 論文の要約の英文への翻訳 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用しない |
| 参考書 | 使用しない |
| 成績評価の方法及び基準 | 授業参画度(30%)、論文の完成度(10%)、論文の学術的貢献度(60%) 授業参画度は、毎回の課題が確実に実行されているかどうかを評価の対象とする。 |
| オフィスアワー | 原則火曜日の4限だが、論文に関する質問は随時メールで受け付ける。 |