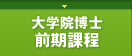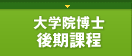検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

考古学ゼミナール1
| 科目名 | 考古学ゼミナール1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 山本孝文 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 史学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業概要 | 論文作成の準備にあたり、考古資料の解釈法を習得する。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 各自の卒業論文を作成するための予備知識を身につける。また、先行研究・分析の実例から、資料解釈の視覚を広げ、各種資料への適用法を学ぶ。 この科目は文理学部(学士(文学))のディプロマポリシーDP6及びカリキュラムポリシーCP9に対応しています。 |
| 授業の方法 | 各自の卒業論文を作成するための予備知識を身につけるため、関心を持っている考古資料の概要をまとめる。また、先行研究・分析の実例を概観し、各自の卒業論文テーマにおける素材(研究対象)の性格と解明可能な内容(研究目的)を検証する。 1ヶ月毎に目標を立てて資料収集を行う時間を設ける。 本授業の事前・事後学習は,各2時間の学習を目安とする。 |
| 履修条件 | 日本史基礎実習または考古学基礎実習(D群設置設置科目)を1単位以上修得していること。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
卒業論文の書き方1 論文とは何か [事前学習]初年次導入科目で使用したテキストを読んでおく [事後学習]レポートへの反映 |
| 2 |
卒業論文の書き方2 テーマ設定の仕方 [事前学習]初年次導入科目で使用したテキストを読んでおく [事後学習]レポートへの反映 |
| 3 |
卒業論文の書き方3 研究史に関わる文献の集め方 [事前学習]初年次導入科目で使用したテキストを読んでおく [事後学習]レポートへの反映 |
| 4 |
卒業論文の書き方4 アウトラインの作り方 [事前学習]初年次導入科目で使用したテキストを読んでおく [事後学習]レポートへの反映 |
| 5 |
各自のテーマの調査と発表1 土器関連研究 [事前学習]発表者は発表レジュメを準備する [事後学習]学習内容のレジュメへの反映 |
| 6 |
各自のテーマの調査と発表2 石器関連研究 [事前学習]発表者は発表レジュメを準備する [事後学習]学習内容のレジュメへの反映 |
| 7 |
各自のテーマの調査と発表3 集落・住居址関連研究 [事前学習]発表者は発表レジュメを準備する [事後学習]学習内容のレジュメへの反映 |
| 8 |
各自のテーマの調査と発表4 金属器関連研究 [事前学習]発表者は発表レジュメを準備する [事後学習]学習内容のレジュメへの反映 |
| 9 |
各自のテーマの調査と発表5 古墳関連研究 [事前学習]発表者は発表レジュメを準備する [事後学習]学習内容のレジュメへの反映 |
| 10 |
各自のテーマの調査と発表6 副葬品関連研究 [事前学習]発表者は発表レジュメを準備する [事後学習]学習内容のレジュメへの反映 |
| 11 |
各自のテーマの調査と発表7 古代関連研究 [事前学習]発表者は発表レジュメを準備する [事後学習]学習内容のレジュメへの反映 |
| 12 |
各自のテーマの調査と発表8 中・近世関連研究 [事前学習]発表者は発表レジュメを準備する [事後学習]学習内容のレジュメへの反映 |
| 13 |
各自のテーマの調査と発表9 その他のテーマ(国内) [事前学習]発表者は発表レジュメを準備する [事後学習]学習内容のレジュメへの反映 |
| 14 |
各自のテーマの調査と発表10 その他のテーマ(海外) [事前学習]発表者は発表レジュメを準備する [事後学習]学習内容のレジュメへの反映 |
| 15 |
まとめと反省 [事前学習]発表内容とレジュメをもう一度見直しておく [事後学習]発表内容とレジュメの点検と反省 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし |
| 参考書 | 小笠原喜康 『最新版 大学生のためのレポート・論文術』 講談社現代新書 2018年 その他授業中に適宜紹介する |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(20%)、授業参画度(30%)、発表(50%) レポートは学期に1回課す。 授業参画度は発表に対する質問・コメントなどの内容や回数を基準に判断する。 |
| オフィスアワー | 授業後ないし個別に時間を設定して教室や研究室で対応 |