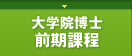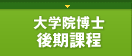検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

日本史研究実習2
| 科目名 | 日本史研究実習2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 堀川徹 | ||||
| 単位数 | 1 | 学年 | 3・4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 史学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業概要 | 日本古代史に関する論文を読み、論文読解能力を養うとともに、受講生全員で討議することで日本古代史の各テーマの理解を深める。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 論文を正しく読み解き理解することができる。 日本古代史の最新の研究状況を理解することができる。 報告に対して自らの意見を述べることができる。 この科目は文理学部(学士(文学))のディプロマポリシーDP6及びカリキュラムポリシーCP9に対応しています。 |
| 授業の方法 | 演習形式。各回2人の報告(1報告あたり30分程度)・質疑(1報告あたり10分程度)をおこなう。そのため受講者数にもよるが、半期で2回以上の報告を担当してもらう。報告内容は日本古代史に関する学術論文の論評で、報告者はレジュメを作成して受講生に配布したうえで報告する。報告で扱う論文は各人が選択した学術論文(2001年以降の史学雑誌の回顧と展望に載せられたものに限る)とする。初回報告で担当する学術論文の割り当ては初回授業時におこなうため、受講希望者は必ず初回授業に出席すること。 |
| 履修条件 | 自主創造の基礎1、及びいずれかの基礎実習(D群設置科目)を1単位以上修得していること。 日本古代史を専攻するものが望ましいが、それ以外の学生も歓迎する。日本古代史以外を専攻する学生は読む論文を配慮する。 前期開講同担当者の日本史研究実習1も履修することが望ましい。 本授業は報告と質疑からなるので、積極的な参加を求める。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 授業の説明、発表順、担当論文の決定 |
| 2 | 研究発表①:学生A・B |
| 3 | 研究発表①:学生C・D |
| 4 | 研究発表①:学生E・F |
| 5 | 研究発表①:学生G・H |
| 6 | 研究発表①:学生I・J |
| 7 | 研究発表①:学生K・L |
| 8 | 研究発表①:学生M・N |
| 9 | 研究発表②:学生A・B |
| 10 | 研究発表②:学生C・D |
| 11 | 研究発表②:学生E・F |
| 12 | 研究発表②:学生G・H |
| 13 | 研究発表②:学生I・J |
| 14 | 研究発表②:学生K・L |
| 15 | 研究発表②:学生M・N |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 教科書は使用せず。各人の報告レジュメ。 |
| 参考書 | 使用しない |
| 成績評価の方法及び基準 | 報告内容(80%)、質疑応答への参画度(20%) 出席することが大前提となる。無断欠席は厳禁。 |
| オフィスアワー | 授業終了後講師室にて |