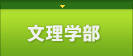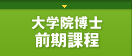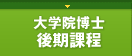検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

総合研究1~8 (NIPPONトークで対話力2018)
| 科目名 平成28年度以降入学者 |
総合研究1~8 (NIPPONトークで対話力2018) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 久保田 裕之 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1~4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 総合教育科目 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | ディスカッションで学ぶ現代日本の社会問題 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 授業を通じて、1)現代の複雑な社会問題についての基本的な知識を身につけるとともに、2)資料に基づいて論理的にディスカッションを行う技術を習得できる。こうした知識や技術は、卒業論文やゼミナールに向けた基礎的な訓練になるだけでなく、就職活動における面接やグループ面接において相手の意見を尊重しながら自分の意見を主張するための訓練としても役に立つ。 |
| 授業の方法 | あらかじめ指定された6つのテーマに関して、1)受講生4人~8人程度でグループを作り、2)講義回でテーマに関する基礎的な事柄を理解したあと、3)翌週までにグループ内で分担して資料を集め、4)討論回で実際の討論を通じてディスカッションの訓練とテーマについての理解を深めていく。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 討論回の前には、事前に示された参考文献や統計資料などをグループで分担してまとめたレジュメを作成してくる必要がある。報告回の前には、書記を中心に前回の討論をまとめた報告資料を作成してくる必要がある。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 授業ガイダンス/準備講義(1):ディスカッションの論理と形式 |
| 2 | 準備講義(2):資料の集め方とディスカッション・レジュメの作り方/次回テーマ講義「大学の歴史」 |
| 3 | 討論(1):「大学で職業訓練を行うべきか」(仮) |
| 4 | 報告(1):前回討論の報告/次回テーマ講義「企業社会と労働」 |
| 5 | 討論(2):「どうすればブラック企業はなくせるか」(仮) |
| 6 | 報告(2):前回討論の報告/次回テーマ講義「差別と是正措置」 |
| 7 | 討論(3):「女性専用車両は男女差別か」(仮) |
| 8 | 報告(3):前回討論の報告/次回テーマ講義「監視社会の光と影」 |
| 9 | 討論(4):「日本の死刑制度はなくすべきか」(仮) |
| 10 | 報告(4):前回討論の報告/次回テーマ講義「結婚と家族」 |
| 11 | 討論(5):「同性婚カップルの養子縁組を認めるべきか」(仮) |
| 12 | 報告(5):前回討論の報告/次回テーマ講義「(未定)」 |
| 13 |
討論(6):「(未定)」(最後のテーマは学生から募集する) 参考:どのような条件であればヒト・クローン技術は容認できるか(2017) |
| 14 | 第2回目から第13回目までの講義内容について質疑応答を行う |
| 15 | 報告(5)/まとめ:前回討論の報告/総評/授業評価 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 『議論のレッスン (生活人新書) (福澤 一吉)』 日本放送出版協会 2002年 テキストには読みやすい新書を選んだので、3回目の授業までに購入しておくこと。授業内で適宜読んでくる箇所を指示する他、折に触れてディスカッションの技術を学ぶために参照する。 |
| 参考書 | 飯田泰之 『ダメな議論――論理思考で見抜く 』 筑摩書房 2006年 講談社 『武器としての決断思考 (滝本哲史)』 2011年 |
| 成績評価の方法及び基準 | 授業参画度(90%)、相互評価(10%) 成績評価は、原則として討論回に提出するディスカッション・レジュメ(全6回)と、ディスカッションへの貢献に対するグループ内での相互評価を基に、総合的に判断する。 |
| オフィスアワー | 授業期間中の月曜昼休み (新)本館4階久保田研究室(407) hkubota@chs.nihon-u.ac.jp |