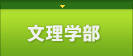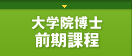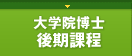検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

卒業論文研究ゼミ1
| 科目名 | 卒業論文研究ゼミ1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 一條 祐哉 | ||||
| 単位数 | 1 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 英文学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 英語の「時制と相」、「前置詞」に関する文献を読み、テーマを絞る。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 「時制と相」、「前置詞」に関する文献を読み、基礎的な知識を確認し、自分のテーマを卒業論文のテーマとしてよりふさわしいものにすることを目指す。 |
| 授業の方法 | 授業は演習形式で、始めに発表担当者に教科書の内容について発表をしてもらい、その後、ディスカッション・質疑応答を行います。 ※ 発表担当者は、ハンドアウトを用意し、聞いている人に分かりやすく、担当箇所の解説(内容・キーワードの解説等)と疑問点の提示(必ず2つ)をしてください。 ※ 発表担当でなくても、毎回全員が発言する機会があります。この授業は皆さんが主役なので、必ず予習をして質問やグループ・ディスカッションなど、積極的に取り組んでください。 ※ 夏期休暇中に勉強会をする予定です。 |
| 履修条件 | 進行形をテーマに考えている人は「英語学演習1」(金2・一條)を、また認知言語学的な内容を考えている人は「英語意味論演習1」(木2・一條)の聴講をすすめる。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | (1) 事前学修として、教科書を批判的に丹念に読み、ノートにまとめる。また、教科書で扱われている概念・言語現象について、類例あるいは反例を探してみる。分からないところは、どこがどのように分からないのかを明らかにし、授業時の質問(必ず1つ用意しておくこと)として備えておく。 (2) 事後学修として、毎回の授業内容を分かりやすくノートにまとめておく。このノートは学期末のレポートで必要となる。 (3) Blackboardを使用し、連絡や資料の配付、課題の回収などをするため、このクラスを登録しておくこと。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | オリエンテーション(授業についての説明、発表の仕方など) |
| 2 |
発表①:Dixon (2005) (1) §7.1(テンスとアスペクトの基本概念) [準備]教科書(pp.209 - 211)を読んで、質問を考えておくこと。 |
| 3 |
発表②:Dixon (2005) (2) §7.2(総称文)- §7.3(未来) [準備]教科書(pp. 211 - 213)を読んで、質問を考えておくこと。 |
| 4 |
発表③:Dixon (2005) (3) §7.3(未来) [準備]教科書(pp. 213 - 215)を読んで、質問を考えておくこと。 |
| 5 |
発表④:Dixon (2005) (4) §7.4(完了・未完了) [準備]教科書(pp. 215 - 217)を読んで、質問を考えておくこと。 |
| 6 |
発表⑤:Dixon (2005) (5) §7.4(現実・前段階) [準備]教科書(pp. 217 - 219)を読んで、質問を考えておくこと。 |
| 7 |
発表⑥:Dixon (2005) (6) §7.4(現在・過去) [準備]教科書(pp. 219 - 221)を読んで、質問を考えておくこと。 |
| 8 |
発表⑦:Dixon (2005) (6) §7.4(現在・過去)- §7.5(非現実・相) [準備]教科書(pp. 221 - 223)を読んで、質問を考えておくこと。 |
| 9 |
発表⑧:Dixon (2005) (7) §7.7(使用される動詞) ※§7.6は割愛 [準備]教科書(pp. 225 - 227)を読んで、質問を考えておくこと。 |
| 10 |
発表⑨:Dixon (2005) (9) §7.7(使用される動詞) [準備]教科書(pp. 227 - 229)を読んで、質問を考えておくこと。 |
| 11 |
発表⑩:Huddleston and Pullum (2002) (1)(空間を表す前置詞) [準備]教科書(pp. 647-649)を読んで、質問を考えておくこと。 |
| 12 |
発表⑪:Huddleston and Pullum (2002) (2)(in, on, at) [準備]教科書(pp. 649-651)を読んで、質問を考えておくこと。 |
| 13 |
発表⑫:Huddleston and Pullum (2002) (3)(意味拡張した前置詞) [準備]教科書(pp. 651-653)を読んで、質問を考えておくこと。 |
| 14 |
質疑応答の上、レポートを作成し、Blackboard上に掲載 [準備]レポートを作成するにあたり、疑問点などをまとめておくこと。 |
| 15 |
レポートについてのコメントと総括、夏期休暇中の課題について [準備]Blackboard上のクラスメートの書いたレポートを読んで、質問を考えておくこと。 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | Dixon (2005) A Semantic Approach to English GrammarとHuddleston and Pullum (2002)The Cambridge Grammar of the English Languageの一部のコピーを教員が用意する。 |
| 参考書 | 英語の辞書を毎回持参すること。 |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(65%)、授業参画度(15%)、教科書の内容についての発表(ハンドアウトも評価の対象)(20%) ※「授業参画度」は、授業への積極的参加態度(自発的発言、質問等)で評価する。 ※ 遅刻および早退3回で1回分の欠席とする。な お、30分以上の遅刻および30分以上前の早退は欠席とする。 ※ 授業中の私語・飲食・居眠り・携帯電話使用等の迷惑行為は減点の対象とする。 |
| オフィスアワー | 授業終了後、教室にて。もしくは水・木・金の16時30分以降、7309研究室にて。 |