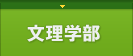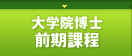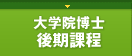検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

日本史特殊講義5
| 科目名 | 日本史特殊講義5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 村井 章介 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 伊達家『塵芥集』から中世社会を読む |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 陸奥の戦国大名伊逹稙宗が天文5年(1536)に作った戦国家法(分国法ともいう)である『塵芥集』は、全171箇条と最大の条数をもつ。これを逐条的に読んで、文意を考える。法文は基本的に仮名書き(濁点なし)なので、まずどういう漢字を宛てるかから解釈は始まる。さらに、法文を通じてどのような中世社会像が見えてくるかを、先行研究における解釈(とくに教科書2における勝俣鎮夫、教科書3における桜井英治・清水克行のもの)を批判的に検討しつつ、参加者全員で議論する。 |
| 授業の方法 | 基本的に、『塵芥集』各条文の音読、逐語訳を基本とし、それが終った後、法典全体や他の条文、御成敗式目等他法典と関係、法文に表れた中世社会の姿などについて、担当者による自由発表を行なう。発表者は原則として1回につき1人。各回の該当部分について、『戦国法の読み方』で議論がなされていれば、その内容を披露する。 『戦国法の読み方』の回では、担当部分の要約、論点の批判的な紹介、異なった解釈の可能性についての議論、などを行なう。 参加者の希望次第で、福島県で現地調査を行なう。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 事前に、各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を読んできて、当日の発言を準備しておく。 各回の担当者は、解釈案を準備して授業に臨み、事後に授業での議論を踏まえた修正を加える。それを学期末に課題として提出する。 授業時間外に60時間の学習を行なう。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | イントロダクション、受講生自己紹介、幹事選出 |
| 2 | 塵芥集 前文・第1~7条の講読(教員による模範発表) |
| 3 |
戦国法の読み方 序、Ⅰ-1・2の検討(学生、以下同じ) 各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を予め読んできて、当日の発言を準備しておく。 |
| 4 |
塵芥集 第8~14条の輪読 各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を予め読んできて、当日の発言を準備しておく。 |
| 5 |
塵芥集 第15~17条の輪読 各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を予め読んできて、当日の発言を準備しておく。 |
| 6 |
塵芥集 第18~19条の輪読 各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を予め読んできて、当日の発言を準備しておく。 |
| 7 |
戦国法の読み方 Ⅰ-3・4の検討 各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を予め読んできて、当日の発言を準備しておく。 |
| 8 |
塵芥集 第20~24条の輪読 各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を予め読んできて、当日の発言を準備しておく。 |
| 9 |
塵芥集 第25~26条の輪読 各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を予め読んできて、当日の発言を準備しておく。 |
| 10 |
塵芥集 第27~30条の輪読 各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を予め読んできて、当日の発言を準備しておく。 |
| 11 |
戦国法の読み方 Ⅱ-1・2の検討 各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を予め読んできて、当日の発言を準備しておく。 |
| 12 |
塵芥集 第31~34条の輪読 各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を予め読んできて、当日の発言を準備しておく。 |
| 13 |
塵芥集 第35~38条の輪読 各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を予め読んできて、当日の発言を準備しておく。 |
| 14 |
塵芥集 第39~41条の輪読 各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を予め読んできて、当日の発言を準備しておく。 |
| 15 |
戦国法の読み方 Ⅱ-3・4の検討 各回の担当者だけでなく、全員が該当部分を予め読んできて、当日の発言を準備しておく。 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 佐藤進一・池内義資・百瀬今朝雄 『日本中世史料集 第三巻 武家家法Ⅰ』 岩波書店 1965年 第1版 石井進・石母田正・笠松宏至・勝俣鎮夫・佐藤進一 『中世政治社会思想 上 (日本思想大系21)』 岩波書店 1972年 第1版 桜井英治・清水克行 『戦国法の読み方 伊逹稙宗と塵芥集の世界』 高志書院 2014年 第1版 日本中世史料集 第三巻 武家家法Ⅰと中世政治社会思想 上は教員がコピーを準備。 戦国法の読み方は学生が購入(2500円+税) |
| 参考書 | 村井章介 『テキスト分析からみた甲州法度の成立過程』 武田史研究54号 2016年 村井章介 『甲州式目(松平文庫本)校訂原文・注釈・現代語訳』 大学院紀要(立正大学大学院文学研究科)34号 2018年 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(20%)、レポート(50%)、授業参画度(30%) |
| オフィスアワー | 授業終了時 |