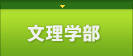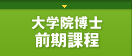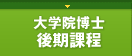検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

中国語学演習1
| 科目名 | 中国語学演習1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 西川 優子 | ||||
| 単位数 | 1 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 中級から上級へ進む段階では、必ずぶつかる大きな壁がある。中国語学習三年目の今、頑張ってこの壁を乗り越えてみよう! 前期:①処置文(“把”の文)②受け身文(“被”の文) 後期:③使役文(兼語文)④“了1”“了2” |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 中国語を話せるようになりたい、これは全ての学生の願いだろう。では、話す、話せるようになるには、どうすればよいのだろうか? その答えは「書く、読む」ことである。拒否反応が返ってきそうであるが、そう難しいことではない。「急がば回れ」の気持ちで徐々に理解していくと、面白さを覚えるようになり、自分に対する自信もついてくる。興味と自信をもって「書く、読む」を続けていく中で、「話す」ことが楽にできるようになっているのに、気付かされることだろう。 |
| 授業の方法 | 毎回、授業の最初に文法事項の説明をし、そのあと例文約20題を日本語に訳していく。受講生は必ず全員当てることとする。日訳のあとは、教師が同文を中国語で聞かせ、口頭日訳の訓練を行う。さらに、同文の日本語を聞かせて、口頭中訳の訓練も行う。授業の最後にポイントをまとめて、次回の予習へとつなげていく。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 事前学習:①例文の単語の発音と意味を、辞書を引いて調べる。 ②例文の日訳をノートに書く。 事後学習:①例文の日訳から中国語に訳し、筆記する。 ●辞書について:授業に集中する観点から、授業中の辞書の使用は認めない。 辞書は自習の時に、大いに活用してほしい。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
ガイダンス:処置文と受け身文のアウトライン。 処置文①処置文に必要なさまざまなプラスアルファについて。 |
| 2 | 処置文②処置文と結果補語の関連について。 |
| 3 | 処置文③処置文と方向補語・様態補語の関連について。 |
| 4 |
処置文④処置文にしなければならないもの。 “把”目的語+動詞“在”場所(ナニナニをドコソコにドウコウする) |
| 5 |
処置文⑤処置文にしなければならないもの。 “把”目的語+動詞“到”場所(ナニナニをドコソコまで/へドウコウする) |
| 6 |
処置文⑥処置文にしなければならないもの。 “把”目的語+動詞“給”相手方(ナニナニをダレダレへドウコウする」 |
| 7 | 処置文⑦まとめの問題(総復習) |
| 8 |
受け身文①受け身文に必要なさまざまなプラスアルファについて。 受け身文に使われる介詞“被、叫、譲、給”について。 |
| 9 | 受け身文②受け身文と結果補語の関連について。 |
| 10 | 受け身文③受け身文と方向補語の関連について。 |
| 11 | 受け身文④受け身文と様態補語の関連について。 |
| 12 |
受け身文⑤介詞フレーズ“把~”との併用について。 書面語の中の受け身文について。 |
| 13 | 受け身文⑥まとめの問題(総復習) |
| 14 | 第2回目から第13回目までの学習内容について質疑応答を行う |
| 15 | 授業(試験+振り返り) |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 授業時にプリントを配布。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(80%)、授業参画度(20%) |
| オフィスアワー | 授業終了時。 |