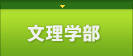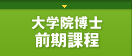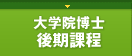検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

卒業論文
| 科目名 | 卒業論文 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 武内 佳代 | ||||
| 単位数 | 8 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 国文学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 日本近現代文学に関する研究成果を形にする |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 3年次から取り組んできた基礎研究や研究課題を土台に、さらに研究テーマを絞り込み、教員の指導をもとに論文執筆を進め、卒業論文の完成を目指す。 |
| 授業の方法 | 基本的に個別に論文指導を行う。授業科目「特殊研究ゼミナール」と課題活動「ゼミ合宿」とも連携させ、口頭発表の時間も確保する。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 個別指導の日程については、学生と相談して決める。 前期は研究計画・研究テーマの再確認と研究発表、作家・作品に関する資料収集と調査・分析、合宿での中間発表を行う。 後期は前期での調査・分析を土台にさらに研究を進め、下書き原稿を書き、指導に基づいて推敲を重ねる。 【事前学修】毎回の課題書や参考論文・参考書を熟読してくる。 【事後学修】授業時に指摘されたことをふり返り、不足していた点を補う。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
卒業論文の構成・テーマについてのガイダンス スケジュールの提示 |
| 2 |
分析する対象・作品を決める 先行研究を集める |
| 3 | 中間報告:学生A・Bの発表と討議 |
| 4 | 中間報告:学生C・Dの発表と討議 |
| 5 | 中間報告:学生E・Fの発表と討議 |
| 6 | 中間報告:学生G・Hの発表と討議 |
| 7 | 中間報告:学生I・Jの発表と討議 |
| 8 | 中間報告:学生A・Bの二度目の発表と再討議 |
| 9 | 中間報告:学生C・Dの二度目の発表と再討議 |
| 10 | 中間報告:学生E・Fの二度目の発表と再討議 |
| 11 | 中間報告:学生G・Hの二度目の発表と再討議 |
| 12 | 中間報告:学生I・Jの二度目の発表と再討議 |
| 13 | 章立てとテーマを再検討する |
| 14 | 草稿を書く |
| 15 | 全体の問題点や課題の整理 |
| 16 |
卒業論文のテーマ・内容について 後期スケジュールの確認、中間論文の提出 |
| 17 | 中間報告:学生A・Bの発表と討議 |
| 18 | 中間報告:学生C・Dの発表と討議 |
| 19 | 中間報告:学生E・Fの発表と討議 |
| 20 | 中間報告:学生G・Hの発表と討議 |
| 21 | 中間報告:学生I・Jの発表と討議 |
| 22 | 中間報告:学生A・Bの再発表と再討議 |
| 23 | 中間報告:学生C・Dの再発表と再討議 |
| 24 | 中間報告:学生E・Fの再発表と再討議 |
| 25 | 中間報告:学生G・Hの再発表と再討議 |
| 26 | 中間報告:学生I・Jの再発表と再討議 |
| 27 | 卒業論文の章立ての最終確認 |
| 28 | 卒業論文の「はじめに」・「おわりに」の確認 |
| 29 | 卒業論文の脚注・参考文献一覧の確認 |
| 30 | 卒業論文の全体の最終確認 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 教科書なし。プリントを使用する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 卒業論文(100%) |
| オフィスアワー | 水曜4限、木曜3限、7号館4階武内研究室。質問等がある場合は事前にメールで予約すること。メールアドレスは授業で知らせる。 |