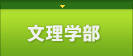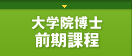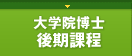検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

卒業論文
| 科目名 | 卒業論文 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 荻野 綱男 | ||||
| 単位数 | 8 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 国文学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 卒業論文の執筆全般に関する指導 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 卒業論文は研究論文である。研究論文は、各自が自分で選んだテーマについて、自分で調べ、自分なりの結論に達することが求められる。とはいえ、学生は論文を書いたことがない場合が大半である。論文執筆の過程で、教員からのさまざまなアドバイスが欠かせない。この授業では、卒業論文執筆予定者が順次発表しながら各自の卒業論文が書けるようになることが目標である。 |
| 授業の方法 | 毎回、3~4人程度が各自のテーマについて発表する。他の参加者からのコメントも歓迎する。 このような自主的な発表を積み重ねながら、自分なりに研究を進め、卒業論文を完成させていく。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 学生の発表がすべてであるし、発表するためには普段から自分のテーマについて研究を進めていかなければならない。その意味では、普段から行っていることすべてが事前学修である。 事後学修は、授業中に出されたコメントを振り返り、自分なりにとらえ直し、論文の方向性を修正したりすることである。 第1回はイントロダクションであり、第2~30回は履修者の発表を毎回3、4名ずつ行う。 毎回の発表内容であるが、その時点での研究の進捗状況に応じて各自が判断すること。一般的には、4月から6月にかけて各種文献調査を行い、自分の研究テーマを決定する。7月から9月にかけて自分で論文に必要なデータを収集する。10月から11月にかけて収集したデータを分析する。12月から論文本体の執筆に入り、1月には推敲を終えて提出である。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | イントロダクション(授業のテーマや到達目標及び授業の方法について説明する) |
| 2 | 第1巡1(4人) |
| 3 | 第1巡2(4人) |
| 4 | 第1巡3(2人)+第2巡1(2人) |
| 5 | 第2巡2(4人) |
| 6 | 第2巡3(4人) |
| 7 | 第3巡1(4人) |
| 8 | 第3巡2(4人) |
| 9 | 第3巡3(2人)+第4巡1(2人) |
| 10 | 第4巡2(4人) |
| 11 | 第4巡3(4人) |
| 12 | 第5巡1(3人) |
| 13 | 第5巡2(3人) |
| 14 | ここまでの各自の途中経過の報告と質疑応答・フィードバック |
| 15 | 第5巡3(4人) |
| 16 | 第6巡1(3人) |
| 17 | 第6巡2(3人) |
| 18 | 第6巡3(3人) |
| 19 | 第6巡4(1人)+第7巡1(2人) |
| 20 | 第7巡2(3人) |
| 21 | 第7巡3(3人) |
| 22 | 第7巡4(2人)+第8巡(1人) |
| 23 | 第8巡1(3人) |
| 24 | 第8巡2(3人) |
| 25 | 第8巡3(3人) |
| 26 | 第8巡4(1人)+第9巡1(2人) |
| 27 | 第9巡2(3人) |
| 28 | 第9巡3(3人) |
| 29 | ここまでの各自の途中経過の報告と質疑応答・フィードバック |
| 30 | 第9巡4(2人) |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 卒業論文自体(100%) 最終的に優れた卒業論文が提出されるか否かがすべてである。 |
| オフィスアワー | 水曜 16:20-17:50 荻野研究室(7410) メールアドレスは授業中に公開する |