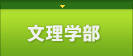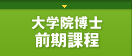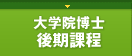検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

生物物理学2
| 科目名 | 生物物理学2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 斎藤 稔 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 生命科学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 生物物理学の最先端分野として生命システムにおける自己組織化現象を学ぶ。複雑な生命システムの形成メカニズムを理解するために必要な基礎知識・技術を学ぶ。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 生物物理学は各階層における生命現象の物理的基礎を理解し、その階層をつなぐ原理原則を見いだすことによって生命現象を解き明かす分野である。このような生物物理学の最先端分野である生命システムにおける自己組織化現象を学ぶことを通して、生物物理学の目的・意義を理解することを目標とする。 生命システムは多様な生体分子・化学反応、極めて多くの細胞から構成される複雑なシステムである。この授業では、そのような複雑な生命システムがどのように形成されるのかを理解するために必要な基礎知識・技術を学ぶと共に、最前線の研究成果に関する知識を身に付ける。 |
| 授業の方法 | 物理システムと生命システムが形成される共通の物理理論を学んだ後、それらの静的な形成メカニズムおよびその事例について話をする。次に、その物理理論の適用限界について話を進め、生命システムに特有な動的な形成メカニズムおよびその事例について話をする。随時、新聞・雑誌記事、論文によって最前線の研究成果を紹介し、最後に課題の文献を読んでもらい、その内容をレポートとしてまとめてもらう。 |
| 履修条件 | なし |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 授業終了時に与える課題について調べ、授業の復習をすること。指示があれば、レポートを作成し提出すること。また、授業終了時に次回授業範囲を説明し資料を配布するので、それを参考にして予習をしておくこと。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
ガイダンス 生物物理学概説、自己組織化現象概説 |
| 2 |
自己組織化現象を学ぶための物理の基礎(1):熱と温度、熱力学第1法則 [準備]第1回目の授業終了時に配布した資料を参考に予習をしておくこと |
| 3 |
自己組織化現象を学ぶための物理の基礎(2):熱力学第2法則 [準備]第2回目の授業終了時に配布した資料を参考に予習をしておくこと |
| 4 |
システムの秩序性を測る物理量、エントロピー [準備]第3回目の授業終了時に配布した資料を参考に予習をしておくこと |
| 5 |
エントロピー的な力とエネルギー的な力、自由エネルギー [準備]第4回目の授業終了時に配布した資料を参考に予習をしておくこと |
| 6 |
静的なシステムの形成メカニズム、静的な自己組織化 [準備]第5回目の授業終了時に配布した資料を参考に予習をしておくこと |
| 7 |
静的な自己組織化の例(1):磁性体、合金 [準備]第6回目の授業終了時に配布した資料を参考に予習をしておくこと |
| 8 |
静的な自己組織化の例(2):タンパク質の構造形成、生体膜の構造形成 [準備]第7回目の授業終了時に配布した資料を参考に予習をしておくこと |
| 9 |
静的な自己組織化の例(3):脳の記憶メカニズム [準備]第8回目の授業終了時に配布した資料を参考に予習をしておくこと |
| 10 |
平衡系と非平衡系、動的なシステムの形成メカニズム、動的な自己組織化 [準備]第9回目の授業終了時に配布した資料を参考に予習をしておくこと |
| 11 |
動的な自己組織化の例(1):ベナール対流、ベロウソフ・ジャボチンスキー反応(BZ反応) [準備]第10回目の授業終了時に配布した資料を参考に予習をしておくこと |
| 12 |
動的な自己組織化の例(2):サーカディアンリズム、細胞周期、解糖サイクル [準備]第11回目の授業終了時に配布した資料を参考に予習をしておくこと |
| 13 |
動的な自己組織化の例(2):筋収縮、神経興奮、脳の動的活動 [準備]第12回目の授業終了時に配布した資料を参考に予習をしておくこと |
| 14 | 学習内容のまとめと質疑 |
| 15 | 試験、解答と解説 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし |
| 参考書 | 授業中に指示する |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(30%)、授業内テスト(40%)、授業参画度(30%) |
| オフィスアワー | 本館6階606号室(斎藤研究室)毎週月曜18時 |