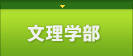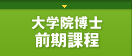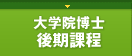検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

数と宇宙2
| 科目名 | 数と宇宙2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 栗田 敬 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1~4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 総合教育科目 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 宇宙における最も基本的な3種類の物理量、長さ、密度、時間が「数」としてどのような値を持っているのかを解説する.宇宙の理解に必要な長さは素粒子レベルの極微小領域から銀河の集団構造まで極めて幅広いスケールに及んでいる.それぞれのスケールに特徴的な構造を解説をする.密度は物質の空間での詰まり具合であり、長さと質量から算出される量である.宇宙においてはこれも真空状態から超高密度星まで極めて幅広いスケールに及ぶ.それぞれの密度において特徴的な現象を解説する.時間スケールも宇宙の誕生、星の誕生と進化、太陽系の誕生と進化において幅広い値を持つ. |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 宇宙に目を向けると我々の慣れ親しんだ日常生活とは大きくかけ離れた世界が拡がっている。この理解の第一歩として大きな幅をもつ3種類の基本的な物理量に注目し、その物理的な背景を解説する.この宇宙の中で地球はどのような場所であるのか、地球を相対視する視点を学んでほしい. |
| 授業の方法 | 通常の講義形式をとる.講義内容や気がついた点を記す講義ノートを取ることをもとめる.講義を聞き分かった気になっても後に何も残らない.自分の言葉で記したノートやメモは、たとえそれが教官の似顔絵であっても、後の考察に大変重要であるというのが私の信念である.そのため講義では資料、ノートなどの配布は行わない.授業内容のまとまり毎に質問事項を小レポートとして提出してもらう.その質問事項に対応したフィードバックを授業時に行う. |
| 履修条件 | なし |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 事前学習として前回の講義内容を復習して講義に臨むことを望む.授業計画に記した準備項目が前回の講義の中心となる項目であり、当日の講義はそれを受けて進める.講義の流れに集中することを望む.講義での疑問点の記入を求める小レポートを講義終了時に求め、次回講義開始時にフィードバックを行う. |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
はじめに:宇宙における3種類の重要な数、長さ、密度・圧力、時間の意味、我々が生きている地球を相対視する視点の重要性 準備:なし |
| 2 |
長さ I:「長さスケール」の基準、地球の大きさ、地球の基準、測地学、エラトステネスの推定、地球上の位置・距離 準備:「相対視」とは何か? |
| 3 |
長さ II:太陽系のスケール、太陽系の構成員、内惑星、外惑星、惑星の大きさ、彗星、太陽系の端とは? 準備:エラトステネスの地球の大きさの推定法とは? |
| 4 |
長さ III:構成のスケール、最も近い星、恒星の大きさの推定法、星の距離の測定法、星の明るさと距離、変光星 準備:太陽系の端はどこか? |
| 5 |
長さ IV:銀河のスケール、星の集団、銀河、大規模な構造、銀河までの距離、一番遠方にある天体、赤方偏移、膨張宇宙 準備:星までの距離の推定法は? |
| 6 |
密度 I:地球の密度、地球の質量の決め方、重力、密度とは?、密度と圧力、地球の平均密度の意味、ニュートン 準備:銀河までの距離はどう測るのか? |
| 7 |
密度 II:太陽系の構成員、惑星間空間、内惑星、外惑星、氷衛星、系外惑星、SuperEarth 準備:地球の平均密度は? |
| 8 |
密度 III:恒星の内部構造、恒星の密度、星の進化、中性子星、状態方程式 準備:氷衛星の密度は? |
| 9 |
宇宙における重力の重要性: 準備:中性子星の質量と大きさはどのように推定するのか? |
| 10 |
時間 I:地球の時間スケール、自転速度、潮汐相互作用、最も正確な時計、地球の自転速度の変化とその原因、年輪、アイスコア 準備:Dark Matter とは? |
| 11 |
時間 II:地球の年齢、測り方、放射性年代、ダーウインとケルビンの論争、放射性元素 準備:潮の満ち引きはなぜ14日周期か? |
| 12 |
時間 III:恒星の一生、太陽と太陽系の年齢、太陽系の形成モデル、初期の太陽系、超新星爆発、隕石 準備:地球の年齢はどのように推定するのか? |
| 13 |
時間 IV:銀河の進化、宇宙の年齢、膨張宇宙 準備:太陽の将来は? |
| 14 |
授業内容の理解度の確認のための授業内試験 準備:ノートを読み返し、授業の流れの復習をしておくこと |
| 15 |
試験の解説及び授業全体を通じての質問を受ける. 準備:各自授業内容の質問を用意してくること. |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(60%)、授業内テスト(20%)、授業参画度(20%) 答案の正確性もさることながら、自分の言葉で表現されているのかという点を重要な評価点とする. |
| オフィスアワー | 授業終了後.e-mail での問い合わせは随時受け付ける. |