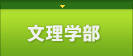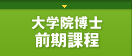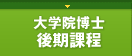検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

英語5(地球科学)
| 科目名 | 英語5(地球科学) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 齋藤 幸子 | ||||
| 単位数 | 1 | 学年 | 2 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 外国語科目 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 英語でまとまったエッセイを書く練習 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | ライティングという、ひとつのコミュニケーションの方法を学びます。各個独立した日本文を英文にするのではなく、ある程度まとまったエッセイが書けるようにもっていくことを目的としています。 |
| 授業の方法 | テキストの各章にある「今回のポイントと参考表現」を使いなgら、エッセイを書いていきます。ポイントの参考表現をまずはじっくり学習してから、そのあとは出来るだけ見ないで、練習問題を予習しておきましょう。授業ではエッセイの和文英訳について、エッセイを書く際の基本的表現、およびエッセイを組みたてる際の構造をテキストに沿って説明・解釈したのち、アットランダムに指名して、予習したテキストの問題を黒板に書いてもらい、添削していきます。各課は2週間で1課の速さですすめていきます。また、4週目は2課分の授業内テストをする予定です。従って、4週目、8週目、12週目は簡単な授業内テストをする予定です。 |
| 履修条件 | ①英語習熟度別クラス分けテストを受け、その結果により振り分けられたクラスで履修すること。 ②英語習熟度別クラス分けテスト未受験の者は、FLEC(外国語教育センター)にて振り分けられたクラスで履修すること。振り分けられたクラス以外での履修はできません。 ③後期は同一教員による同一時限の「英語6」を履修すること。 ④卒業に必要な外国語科目として「英語」を選択した場合、必ずこの科目を履修すること。(中国語中国文化学科及びドイツ文学科の学生は除く。) |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | <事前学修>・<事後学修>ともテキスト予習・復習を徹底してください。 。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス(授業のテーマや到達目標及び授業の方法について説明する |
| 2 | Lesson 1(2) Computer Society コンピュータ化によって滅びる職業 |
| 3 | Lesson 2 (1) Deforestation 森林破壊の原因と結果 |
| 4 |
Lesson 2 (2) Deforestation 森林破壊をめぐる富める国と貧しい国 テストと解説 |
| 5 | lesson 3 (1) Biotechnology バイオテクノロジーで何が可能か |
| 6 | Lesson 3 (2) Biotechnology DNA鑑定は何を解明してくれるか |
| 7 | Lesson 4 (1) 英語を国際語とするべきか |
| 8 |
Lesson 4 (2) English and Internationalization なぜ英語を学ぶことが必要か テストと解説 |
| 9 | Lesson 5 (1) English and Internationalization 地球温暖化の起こる過程 |
| 10 | Lesson 5 (2) Global Warming 地球温暖化がもたらす結果 |
| 11 | Lesson 6 (1) Bullying なぜいじめは起こるか |
| 12 |
Lesson 6 (2) bullying 過去と現在ではいじめの性格に変化はあるのか テストと解説 |
| 13 | Lesson 7 (1) Aging Society なぜ日本では高齢化が進んでいるのか |
| 14 | 事前に示した課題「少子・高齢化によって栄える産業と衰退する産業」について質疑応答を行う |
| 15 | これまでの復習を行い授業のりかいを深める |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 石谷 由美子 『Point by Point (トピック別エッセイの書き方)』 南雲堂 2014年 第6版 |
| 参考書 | プリントを配布して、授業の充実を図る。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(40%)、平常点(5%)、レポート(10%)、授業内テスト(40%)、授業参画度(5%) 小テストは回数で割った平均点(40%)+期末テスト(40%)+レポート(10%)+平常点(5%)+授業参画度(授業態度を含む5%))=100点 とする。 |
| オフィスアワー | 授業終了時 |