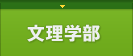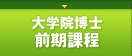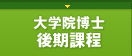検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

考古学特殊研究8
| 科目名 | 考古学特殊研究8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 鈴木 保彦 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 講義の主題は、縄文時代文化研究であるが、特にこの授業では縄文時代の葬墓制と縄文原体研究を主要なテーマとする。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 講義の前半では、縄文時代の葬墓制研究のうち社会論にかかわる主要論文を取り上げ、この分野の研究がこれまでどのように行われてきたかを理解させるとともに、今後の研究を展望する。また後半では、縄文原体の実際ついて実践的に講義し、これについての基本的理解を深める。 到達目標としては、葬墓制研究に関する先行研究と縄文原体について正しく理解し、それらを踏まえて論文執筆や発掘調査報告書の作成など今後の研究活動に反映させることができる能力を習得することにある。 |
| 授業の方法 | 葬墓制研究では、個々の研究論文のコピーを配布し、講読しながらそれらの学史的意義、学ぶべき点、問題点などについて解説し、今後の研究の方向性等について考えるが、扱う項目としては「墓制論と社会論」、「葬墓制研究と分子人類学の成果」などを予定している。また、縄文原体研究では、講義とともに実際に縄を撚ってもらい多種多様な縄文原体について理解を深めさせたい。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 個々の研究論文のコピーについては、すべて事前に配布するので本文を熟読するとともに引用・参考文献等関係文献についても目を通しておくこと。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
葬墓制研究3 墓制論と社会論 (1)林 謙作 1977「縄文期の葬制 第一部 研究史」 『考古学雑誌』62巻3号 |
| 2 | (2)林 謙作 1977「縄文期の葬制 第二部 遺体の配列、とくに頭位方向」 『考古学雑誌』63巻3号 |
| 3 | (3)春成秀爾 1995「葬制と親族組織」 『展望考古学』考古学研究会 |
| 4 | (4)山田康弘 1995「多数合葬例の意義」 『考古学研究』42巻2号 |
| 5 | (5)渡辺 新 1991「縄文時代集落の人口構造 千葉県権現原貝塚の研究Ⅰ』 |
| 6 | (6)田中良之 1998「出自表示論批判」 『日本考古学』第5号 |
| 7 | (7)「墓制論と社会論」の総括と問題点 |
| 8 |
葬墓制研究4 分子人類学の成果 (1)篠田謙一ほか 1998「DNA分析と形態データによる中妻貝塚出土人骨の血縁関係の分析」 『動物考古学』11号 |
| 9 | (2)西本豊弘 2001「DNA分析による縄文後期人の血縁関係」 『動物考古学』16号 |
| 10 |
縄文原体研究 鈴木保彦編 2000 「山内清男 縄文講義ノート-於:東京大学理学部人類学教室」 『縄文時代』第11号 (1)縄文研究の学史 |
| 11 | 〃 (2)縄文原体の実際 ① 0段・1段(無節)・2段(単節)・3段(複節)の縄文 |
| 12 | 〃 (3)縄文原体の実際 ② 多条縄文、反撚(撚り戻し))の縄文 |
| 13 | 〃 (4)縄文原体の実際 ③ 合撚りの縄文(前々段・直前段合撚り、反撚り正撚りの合撚り) |
| 14 | 〃 (5)縄文原体の実際 ④ 結束縄文、付加条の縄文、組紐 |
| 15 | 縄文原体研究総括 |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(70%)、授業参画度(30%) |
| オフィスアワー | 授業内でE-mailアドレスを伝えるので適宜連絡して下さい。 |