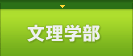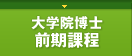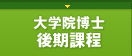検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

現代日本語学2
| 平成28年度以降入学者 | 現代日本語学2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度以前入学者 | 現代日本語学2 | ||||
| 教員名 | 荻野 綱男 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2~4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
| 科目群 | 国文学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 計量日本語学 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 受講者は、計量的にものを見るとはどういうことか、その見方を日本語の諸現象に当てはめて考えるとどうなるかを理解するとともに、実際、そのような見方ができるようになることが目標である。 |
| 授業の方法 | 荻野の講義が中心だが、宿題がかなり出る。受講者は講義の理解と宿題の提出に加えて、計量的な考え方を用いたレポートが求められる。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 計量日本語学は、受講者の多くにとって目新しい内容になるものと思われる。そのため、事前学修よりも事後学修に重点を置く方が理解しやすく効率がよいと思われる。 事前学修としては、以下に示す参考書などを用いて、さまざまな統計手法やその考え方を自分で調べてみることをおすすめする。授業で扱う内容と少しずれるかもしれないが、関連する部分も多いので、内容の理解に役立つだろう。 事後学修としては、毎回のように出される宿題を自力で解くことが重要である。授業の内容を理解していればそうむずかしい話ではないが、自分で電卓で計算することを通じて、計算のプロセスや考え方が理解できるという一面も持つ。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | イントロダクション |
| 2 | 尺度と分析技法 |
| 3 | 基本的な計算――パーセンテージと平均など―― |
| 4 | 統計学の種類と言語統計 |
| 5 | 平均値の差の検定 |
| 6 | 相互独立型の比率の差の検定(1)考え方 |
| 7 | 相互独立型の比率の差の検定(2)応用 |
| 8 | サインテストと相互依存型の比率の差の検定 |
| 9 | カイ二乗検定(1)考え方 |
| 10 | カイ二乗検定(2)応用 |
| 11 | サンプリングと有意差検定の必要性 |
| 12 | 交互平均法とレポートの課題 |
| 13 | 交互平均法の補足 |
| 14 | 課題学習(レポートの執筆) |
| 15 | 過去の研究文献の検討 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし。プリントを用意する。 |
| 参考書 | 荻野綱男・田野村忠温 『 質問調査法と統計処理 (講座 ITと日本語研究 第8巻)』 明治書院 2012年 第1版 荻野綱男他 『日本語の計量研究法 (日本語学Vol.20 No.5 4月臨時増刊号)』 明治書院 2001年 第1版 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(20%)、レポート(80%) |
| オフィスアワー | 水曜日 16:20-17:50 |