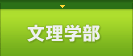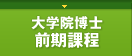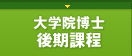検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

日本考古学概説1
| 平成28年度以降入学者 | 日本考古学概説1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度以前入学者 | 日本考古学概説1 | ||||
| 教員名 | 山本 孝文 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 史学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 日本考古学の歴史と研究成果を知る |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 日本において近代学問としての考古学がどのように成立し、どのような過程を経て現在の状況に至ったのかを理解する。 様々な論争や発掘・発見を通じて形作られた考古学的時代区分とそれぞれの時代像を、代表的な遺構・遺物を通じて概観する。 |
| 授業の方法 | プロジェクターの映像を用いて遺跡の写真や図面を提示しながら講義する。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 高校までの日本史教科書で学習した原始・古代の部分ないし各時代の遺跡に触れた部分を再確認しておくこと。 授業中に提示する日本考古学の概説書を通読しておくこと。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
ガイダンス 考古学はどのような学問か [準備]高校の日本史教科書の原始部分を読んでおく |
| 2 |
日本における「遺跡」の認識 [準備]身近な遺跡に何かあるか調べ認識しておく |
| 3 |
日本における考古学の成立 大森貝塚とモース [準備]高校の日本史教科書の原始部分を読んでおく |
| 4 |
土器の認識と役割 縄文土器と弥生土器 [準備]日本考古学の概説書の関連部分を読んでおく |
| 5 |
古墳の発掘と解釈 人類学会とコロボックル [準備]日本考古学の概説書の関連部分を読んでおく |
| 6 |
弥生集落の発掘 唐古・鍵と登呂 [準備]日本考古学の概説書の関連部分を読んでおく |
| 7 |
旧石器時代の認識 明石原人と岩宿の発見 [準備]日本考古学の概説書の関連部分を読んでおく |
| 8 |
編年と論争 縄文土器とミネルヴァ論争 [準備]日本考古学の概説書の関連部分を読んでおく |
| 9 |
発掘と発見の時代1 古代都城の発掘と保存 [準備]日本考古学の概説書の関連部分を読んでおく |
| 10 |
発掘と発見の時代2 高松塚古墳の発見 [準備]日本考古学の概説書の関連部分を読んでおく |
| 11 |
発掘と発見の時代3 吉野ヶ里と三内丸山 [準備]日本考古学の概説書の関連部分を読んでおく |
| 12 |
発掘と発見の時代4 荒神谷・加茂岩倉・黒塚 [準備]日本考古学の概説書の関連部分を読んでおく |
| 13 |
日本考古学の課題1 前期旧石器捏造とその背景 [準備]日本考古学の概説書の関連部分を読んでおく |
| 14 |
日本考古学の課題2 遺跡保存に関わる諸問題 壁画・集落・古墳 [準備]日本考古学の概説書の関連部分を読んでおく |
| 15 |
日本考古学の課題3 年代論争の再燃 弥生時代のはじまりは? [準備]日本考古学の概説書の関連部分を読んでおく |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし |
| 参考書 | 授業内で適宜提示する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(10%)、授業内テスト(60%)、授業参画度(30%) |
| オフィスアワー | 授業終了後 |