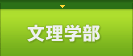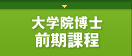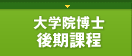検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

******
| 科目名 平成28年度入学者 |
****** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 平成27年度以前入学者 |
宗教学演習7 | ||||
| 教員名 | 合田 秀行 | ||||
| 単位数 | 1 | 学年 | 2~4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 哲学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 『大乗起信論』を読み解く |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 紀元前後のインドに起こった仏教革新運動を大乗仏教と呼びますが、この流れが中国を経て日本に伝播しました。この大乗仏教の根本教義を理論と実践の両面から手際よく要約したのが、5~6世紀に成立した『大乗起信論』であり、中国・日本の読者に愛読され、大きな影響を与えてきました。今回は,このテキストの講読を通して、大乗仏教の本質を理解することを目標とします。 |
| 授業の方法 | 指定したテキストを輪読しながら、基本的に講義形式で解説していきます。原文の書き下し文と訳者の現代語訳を並行させて、進めていきます。仏教用語の特殊な読み方にも慣れてもらいます。また、講義の中では積極的に質問するように心がけて下さい。テーマによっては,討論形式でより理解を深めていく予定です。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 2回目以降については、具体的にテキストを講読(受講生に少しずつテキストを読んでもらいます)していきますので、予め指示した範囲の原文と現代語訳を読んで予習しておくこと。可能な限り、仏教用語の意味や読み方については、仏教辞典やインターネットを活用して調べた上で、講義に臨むことを推奨します。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス 講義の進め方、使用テキストおよび主要な参考文献の紹介 |
| 2 | 『大乗起信論』とはどのようなテキストであるのか、仏教思想史の流れを概説し、その位置づけを解説します。 |
| 3 | 『大乗起信論』の講読(1)序文・因縁分・立義分 [準備]テキスト16-22ページを読んでおくこと。 |
| 4 | 『大乗起信論』の講読(2)解釈分・顕示正義 [準備]テキスト22-29ページを読んでおくこと。 |
| 5 | 『大乗起信論』の講読(3)解釈分・顕示正義 [準備]テキスト30-39ページを読んでおくこと。 |
| 6 | 『大乗起信論』の講読(4)解釈分・顕示正義 [準備]テキスト40-49ページを読んでおくこと。 |
| 7 | 『大乗起信論』の講読(5)解釈分・顕示正義 [準備]テキスト50-59ページを読んでおくこと。 |
| 8 | 『大乗起信論』の講読(6)解釈分・顕示正義 [準備]テキスト60-67ページを読んでおくこと。 |
| 9 | 『大乗起信論』の講読(7)解釈分・対治邪執 [準備]テキスト68-75ページを読んでおくこと。 |
| 10 | 『大乗起信論』の講読(8)解釈分・分別発趣道相 [準備]テキスト76-89ページを読んでおくこと。 |
| 11 | 『大乗起信論』の講読(9)修行信心分・前半 [準備]テキスト90-97ページを読んでおくこと。 |
| 12 | 『大乗起信論』の講読(10)修行信心分・後半 [準備]テキスト98-107ページを読んでおくこと。 |
| 13 | 『大乗起信論』の講読(11)勧修利益分・流通分 [準備]テキスト108-111ページを読んでおくこと。 |
| 14 | 『大乗起信論』に対する現代的評価を巡る考察 |
| 15 | まとめ レポート提出 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 宇井伯寿、高崎直道 『大乗起信論 (岩波文庫 青308-1)』 岩波出版 |
| 参考書 | 参考書についての詳細は授業中に指示します。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(40%)、レポート(60%) 全体の2/3以上、出席している者のみを評価の対象とする。平常点は、テクストの輪読はもとより、質疑・討論などでの発言状況による。レポートは、演習での講読内容を十分に踏まえた上で作成することが条件。 |
| オフィスアワー | 場所は、2号館12階の合田研究室。時間については、原則的に講義終了後とします。 |