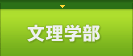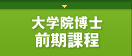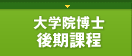検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

**********
| 科目名 平成28年度入学者 |
********** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 平成27年度以前入学者 |
健康・スポーツ実践1~12(集中・スノーボード) | ||||
| 教員名 | 伊佐野 龍司 | ||||
| 単位数 | 1 | 学年 | 2 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 総合教育科目 | ||||
| 学期 | 集中 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | スノーボードを使用した滑走を実践する |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 1年次に学習した「身体知」と「科学知」について実践を通じ統合することで,より幅広い教養を身につけ,より深くスポーツを理解する。 |
| 授業の方法 | 現在ではスキーと並んでスノースポーツの代表であるスノーボードの技術体系,安全管理などについて講義を行う。実習(ゲレンデ実習)では,初級レベルに応じた条件を準備し,少人数により,技術をステップアップさせるための滑走練習を行う。安全を考慮しながら,様々なターン滑走状況を設定して,自由にスノースポーツを楽しむこと,挑戦することを体験する。 |
| 履修条件 | 実習授業は長野県にある志賀高原において3泊4日の日程で行う。そのため,宿舎やスキー場などにおけるルールやマナーの順守,および厳しい自然環境の中での安全管理と協同を求める。 本科目はスノーボードの初心者と初級者を対象としており,授業内容もそれに沿っている. |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 実技授業が行われる低温低酸素環境を調査し,障害予防のための行動の仕方や対処方法を理解しておくこと。さらに安全を自ら確保するために,スノーボード滑走の基本的な動きと起こりうる傷害を確認しておくこと。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス(スノーボード実習の目的,準備,方法,注意点など) |
| 2 | <講義>スノーボードの滑走技術体系,安全管理,自然環境との関わり |
| 3 |
<第3回以降は実技>班編成,環境とスノーボードに慣れる 安全と防寒,マテリアルの構造と機能および装着,移動 |
| 4 |
スノーボードに慣れる(1) 前足固定による推進滑走 安全の確保,ゲレンデでの移動と待機の基本 |
| 5 |
スノーボードに慣れる(2) 前足固定によるフロントサイドターンとバックサイドターン 安全な転び方 |
| 6 |
スノーボードで滑り降りる(1) 両足固定の横滑り(サイドスリップ) リフトの利用方法,ゲレンデでの待機と移動 |
| 7 | スノーボードで滑り降りる(2) 両足固定のサイドスリップ(バックサイドとフロントサイド) |
| 8 | スノーボードで安全に移動する 木の葉落とし(サイドスリップしながら任意の方向に移動) |
| 9 | ターンをする(1) バックサイドターンによるロングターン,大きな動作によるスムーズな切り換え |
| 10 | ターンをする(2) バックサイドターンとフロントサイドターンによる単独のロングターン |
| 11 | ターンをする(3) 緩斜面での連続ロングターン,立ち上がり動作とサイド切換えの連携 |
| 12 | ターンをする(4) 緩斜面での連続ショートターン,膝の角度と下腿前傾によるターンの調整 |
| 13 |
ターンをする(5) カービングターンの基礎 斜面変化や自然環境の変化を楽しみながら長距離を移動 |
| 14 | スキルチェックと理解度の確認 |
| 15 | まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 実習用資料(小冊子)を配布する。 |
| 参考書 | なし |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(40%)、授業参画度(60%) |
| オフィスアワー | 体育学研究室,平日8:30~16:30,土曜日8:30~12:30 |
| 備考 | スノーボードの初心者・初級者を対象とする. 安全を確保するため,少人数による実習授業を行う.本年度は20名で実施する. また,履修希望者が15名に達しない場合は実施しないこともある. なお,事前説明会には必ず出席すること. |