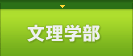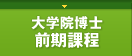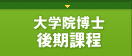検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

地球システム科学概論3
| 科目名 | 地球システム科学概論3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | (上記科目名は2008~2013年度入学者)「地球システム科学概論3」(2004~2007年度入学者) | ||||
| 教員名 | 山川 修治・大八木 英夫 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
| 科目群 | 地球科学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 地球をめぐる大気・水と気候変動 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 地球の水圏と大気圏における多様な現象について,それぞれ地球的視野から捉え,地域性や メカニズムについて理解する。また,諸現象の人間活動との関係について考察する。技術士に 関連する地圏・水圏・気圏分野の基礎概念を導入する。 気水圏科学の立場から,天気変化・異常気象・気候変動について考える(1~8)。 水循環・水収支の立場から海洋・陸水のシステムについて理解する(9~14)。 学科プログラムの学習・教育目標「(A)地球システムの多面的理解」(6、9、14)、「(D)専門技術」(1~15)に寄与する。 ※括弧内の数字は授業計画内の講義番号 |
| 授業の方法 | 図表・写真・画像をプリント・書画カメラ・パワーポイント・ビデオ等を用い示し,現象や観 測結果を具体的に把握できるように努めながら講義を進める。また,下記の授業以外に野外実 習を行う場合がある。 |
| 履修条件 | なし |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 前回授業のまとめを事前学習として行い、次回授業時に提出すること。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
地球の気水圏諸現象を概観してみると ―この概論で何を学ぶか― |
| 2 |
日々の天気変化と雲の挙動 ―衛星雲画像と関連データの併用― |
| 3 |
天気図の基礎と活用 ―気圧・風・降水の関連性を理解する― |
| 4 |
異常気象・天候異変の発生メカニズム ―2013年の特異な現象を探る― |
| 5 |
エルニーニョ・ラニーニャの要因と影響 ―海気相互作用の理解を深める― |
| 6 |
Geofesポスター展での学習 ―地球科学研究のトピックスを考える― |
| 7 |
数年規模でみた気候変動 ―火山大噴火などの気候へのインパクト― |
| 8 |
数10年規模でみた気候変動 ―海面水温・太陽活動の影響― |
| 9 |
大気と陸域の相互作用 ―水循環と水収支― |
| 10 |
海洋と陸水の相違 ―「水」の化学と物理― |
| 11 |
陸域における水の役割 ―侵食・堆積によってできる「水」の器― |
| 12 |
小宇宙としての湖沼 -「水」の中の生態系- |
| 13 |
陸水の水環境・災害 ―集中豪雨・洪水・気温異常― |
| 14 |
水の世界地図 ―資源としての「水」― |
| 15 | まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 部分的に『新訂地学図解』(第一学習社)を使用する。適宜プリントを配布する。 |
| 参考書 | 授業中に紹介する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(50%)、レポート(35%)、授業内課題およびミニレポート(15%) レポート、授業内課題およびミニレポート、試験を含めて総合的に判断し, 60点以上を合格とする。 <達成度評価基準>※括弧内の数字は授業計画内の講義番号 1.身近な気水圏現象,日本付近特有の気象について,その概略の成り立ちを理解したか。(1~3) 2.異常気象・天候異変・気候変動のメカニズム,地球科学全般について基本を把握したか。 (4~8) 3.水圏科学に関する,機構・現象の基本を理解したか(9~12)。 4.諸地域の水環境における問題について理解したか。(13・14) |
| オフィスアワー | 随時 8号館 A312室(山川) A216室(大八木) |
| 備考 | レポート課題(山川担当分):地球システム科学科「Geofestivalポスター展」を見学し(上記第6回目)、3年生部門から 1点、4年生(以上)部門から2点を選んでまとめ、考察する。 |