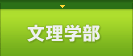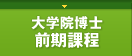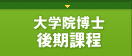検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

社会福祉演習1
| 科目名 | 社会福祉演習1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 諏訪 徹 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | コース科目 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 社会福祉を掘り下げる力を身につける |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | ある福祉的課題が認識された時、その課題に対応する実践が企図されたり、制度の創設や見直しが行われる。社会福祉の政策や実践は、常に新しい社会課題に直面し、変化しているのである。 本演習では、実際の社会福祉政策を素材に、政策課題がどのように認識されたのか、どのような政策が企図されたのか、政策は実践や暮らしにどんな変化をもたらしたかを、政策形成の資料やデータ、ディスカッションを通じて読み解いていく。これにより、多角的な問題分析、資料収集、政策形成過程の追跡、各種制度の連関の理解など、福祉政策や福祉実践を掘り下げ、リアリティをつかむための作法や力量を身につける。 前期は、生活困窮や社会的孤立者などを支援する制度として現在企画されている生活困窮者支援制度を素材に、社会福祉政策の掘り下げ方を学んでいく。 後期は、各自がテーマを定め、各自の資料分析、報告、全体でのディスカションを行いながら、最終的に各自レポートを作成する。福祉政策や福祉実践を深く調べ、分析、評価する基礎的な作法を習得することが目的であるから、各自のレポートのテーマは、介護、障害、児童、低所得、ホームレス、地域福祉、福祉NPO、社会的企業、司法福祉、教育福祉、国際福祉、専門職制度etc、なんでもかまわない。 |
| 授業の方法 | ・新聞記事、審議会資料などを用いて、現実の社会問題や政策にふれながら学ぶ。 ・個人ワーク、グループディスカッションなど自ら考え、発言する演習を行う。 ・調査や分析力を養うため、事前・事後の資料調査、レポート作成等を課す。 ・授業中提示した参考文献等の学習を奨励する。 |
| 履修条件 | 社会福祉コース履修学生 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | イントロダクション |
| 2 | 生活困窮者支援制度とは |
| 3 | 問題の現状と課題、問題発生の要因を分析する |
| 4 | 問題の現状と課題、問題発生の要因を分析する |
| 5 | 問題の現状と課題、問題発生の要因を分析する |
| 6 | 実践の現状と課題を分析する |
| 7 | 実践の現状と課題を分析する |
| 8 | 実践の現状と課題を分析する |
| 9 | 政策形成過程を分析する |
| 10 | 政策形成過程を分析する |
| 11 | 政策形成過程を分析する |
| 12 | 生活困窮者支援制度の分析のまとめ |
| 13 | 各自の研究テーマのプレゼンテーション |
| 14 | 各自の研究計画の立案 |
| 15 | 各自の研究計画の立案 |
| 16 | テーマについての資料・データの報告とディスカション(その1) |
| 17 | テーマについての資料・データの報告とディスカション(その1) |
| 18 | テーマについての資料・データの報告とディスカション(その1) |
| 19 | テーマについての資料・データの報告とディスカション(その1) |
| 20 | テーマについての資料・データの報告とディスカション(その2) |
| 21 | テーマについての資料・データの報告とディスカション(その2) |
| 22 | テーマについての資料・データの報告とディスカション(その2) |
| 23 | テーマについての資料・データの報告とディスカション(その2) |
| 24 | レポートの報告とディスカション |
| 25 | レポートの報告とディスカション |
| 26 | レポートの報告とディスカション |
| 27 | レポートの報告とディスカション |
| 28 | 総括的講義とディスカッション |
| 29 | 総括的講義とディスカッション |
| 30 | 総括的講義とディスカッション |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(60%)、授業参画度(40%) |